 leins=pallange » 日志
leins=pallange » 日志
飛び立つ君の背を見上げる 摘录笔记
2021-2-13 23:49 /
勢いがないと書けへん!
想摘录就摘录了没啥门槛或者标准 这次吐槽比较少
直接复制出来的 注音基本没修见谅
Q5 高校生活の忘れられない思い出は?
Q6 あなたがいちばん好きな先生は?
Q7 将来きっと大物になると思う人物は?
Q12 あなたが友達に抱いている印象は?
Q13 あなたの自分自身への印象は?
値段は確か、百万円近くしたはずだ。吹奏楽部で使用される管楽器のなかでもオーボエはかなり高額な部類に入る。
「世界でいちばん難しい木管楽器」としてギネスブックに登録されていたりする。
「捕まえたら食べられそう」
「何を?」
「光」
「そういやさ、吹部の卒業旅行はどうする? 去年の先輩らはスキー行ったらしいけど」
話題を振った夏紀の左側に希美が、右側に優子が並んで歩く。四人でいるときは前後の列で二人、二人になることが多いけれど、三人のときはこうして一列になる。だが、これがみぞれを含めた三人になると、なぜかみぞれと二人に分かれてしまう。みぞれが浮いているとかそういうわけじゃない。ただ、みぞれは一人になりがちな子だった。
「それでええやん。入試の日程が全部終わった時期がええやろな、三月下旬とか」
面倒なことはさっさと忘れて、楽しかったことだけを覚えていたい。好きなもの、好きな人、それだけに脳のリソースを割きたい。
「みぞれ、あんま歌わんからなー。タンバリンばっか叩たたいてるやんあの子」
全国大会後、三年生だけで行った打ち上げの様子を思い出し、夏紀の口元は自然と緩んだ。
「アントワープブルーね」
アントワープブルーは最近メジャーデビューを果たした四人組ロックバンドだ。
最近では映画の主題歌を担当するなど、活躍がめざましい。
「ネットで買ってダウンロードすればいいのに」
そう告げる希美に、わかってないなと夏紀は首を左右に振る。
「こういうのはちゃんと店で買いたいの。予約して、発売日に受け取る。フィルムを剥がすあのドキドキ感までが一連のイベントなワケよ」
誰かを気にせずに歩くのは好きだ。一人でいるのが好き。だけど、ずっと一人でいるのはちょっとだけ寂しい。
男性ボーカル
昔から、夏紀はパンクやロックといった激しい音楽が好きだった。クラシックみたいなお行儀のいい音楽は退屈だし、自分の肌には合わないと感じていた。だけど、吹奏楽部に入ってからそうしたものへの見方も少し変わった。それがいいことなのか悪いことなのか、自分でもよくわからない。
一月の風が、夏紀の頬に突き刺さる。
頭に立派がつくようなものにはなりたくない、大人にだってなりたくない。
棚に飾られたCDケースのすぐ隣には、後輩たちからもらった写真立てが飾られていた。木製のフレームには、夏紀の好きな熊のマスコットキャラクターが描かれている。
//第1话的开篇插图

夏紀の服の好みは、好きなバンドの影響を大いに受けている。可愛かわいいよりもカッコよくなりたいし、パステルカラーよりはビビッドカラーのほうが好きだ。ダメージジーンズもレザージャケットも大好きだし、髪の毛もいつかは染めたいと思う。
それとは逆に、優子は清せい楚そ系ファッションを好む。吹奏楽部時代の憧れの先輩がそうした格好をしていたせいだ。リボンやフリルのついた服装が好きで、流行の小物をセンスよく取り入れている。
「夏紀は希美派やからしゃあないか」
「じゃ、優子はみぞれ派やな」
「当たり前やん」
「そこ、自分で認めるんや」
「あの子、ずっと一生懸命やったやんか。ああいう子が報われてほしい」
「希美だって一生懸命やったけどね」
「希美とみぞれじゃ、一生懸命の種類が違うやん」
「それはなんとなくわかる」
「でしょ」
中学三年生のとき、夏紀と希美は同じクラスだった。南中は一学年が四クラス
夏紀たちが通っていた南中では、毎年一月の第三木曜日に大縄跳び大会が開催されることになっていた。クラスごとに男女に分かれて大縄を跳び、回数を競い合う。優勝したからといってとくに賞品があるわけでもなく、得られるのは名誉だけだ。
夏紀たちのクラスは学年四クラス中三位という中途半端な結果となった。
夏紀が受験した北宇治高校は、東中出身の子が全校生徒の五割を占める。南中の子も少なくはないが、圧倒的に多いというわけでもない。
「ほかに南中の子はいいひんの? 吹奏楽部の子とか」
「菫すみれは一緒やってんけど、ほかは別のクラスやねんなあ」
「菫? あぁ、若わか井いさんね」
若井菫とは夏紀も中学一年生のときに同じクラスだった。ほとんどしゃべったことはないが、派手な白縁眼鏡が特徴的だったから顔だけはよく覚えている。
「菫はサックスがめちゃくちゃ上手いねん。高校でも一緒に吹奏楽部に入るって約束しててさ」
「夏紀、南中の吹奏楽部員が何人いたか知ってる?」
「知るわけないやん」
「うちが部長だった代で八十三人。うちの学年はとくに多くて三十四人いた。で、例年だと南中の子は三割くらいが北宇治に進学する」
「うち、夏紀はパーカッションとか向いてると思うねんなぁ」
//一开始被认为适合打鼓hhh 确实很搭
「初心者ちゃんは、これやっとけばとりあえず大丈夫」
そう言って夏紀に楽譜を渡してきたひとつ上の先輩──田た中なかあすかは、全学年の部員たちから一目置かれていた。楽器も上手い、頭もいい、さらにはやたらと口が回る。その先輩さえいれば、低音パートには何ひとつ困った問題は起こらなかった。同じ学年の友人たちは優しい性格で、揉もめ事もほとんどなかった。
//来了 明日香天下第一
今年の南中出身の一年生は九人で、夏紀を除いた八人が経験者だった。しかも中学時代に関西大会出場を果たしているだけあって、どの子も演奏が上手い。サボりが当たり前の北宇治の吹奏楽部で、ここにいる夏紀以外の八人が先輩に目をつけられるのは致し方のないことだった。
「はー、副顧問が顧問になってくれたらええのに」
「そんなんしたら今度は三年が暴れ散らして収拾つかんでしょ。ってか、いまの三年は顧問を懐柔することで副顧問に対抗してんねんから。顧問と三年生は、副顧問が口出ししないようにするって方向では利害が一致してる」
北宇治の吹奏楽部の顧問は梨り香か子こ先生という二十代後半の女性教師で、やる気のない三年生部員によく振り回されていた。
副顧問の松まつ本もと先生は五十代のベテラン音楽教師で、とにかく厳しいことで有名だった。本来ならば顧問になるべき存在なのだろうが、家庭の事情で副顧問に収まっているらしい。吹奏楽部にあまり介入しないのは、顧問である梨香子先生に気を遣ってのことだろうという噂うわさもあった。梨香子先生は松本先生がいると露骨に萎縮していたからだ。そんな大人の事情、こちらからすると知ったことではないのだけれど。
南中出身の一年生たちは、梨香子先生を軽蔑していた。
「オーボエに先輩はいない」
「みぞれってさ、なんでオーボエ選んだん?」
問いかけに、みぞれの瞳がそろりと動く。闇色をした瞳に、前を歩く希美の後ろ姿が映り込む。
「希美が言ったから」
「オーボエをやれって?」
「違う。吹奏楽部に入らないかって」
「みぞれと希美は幼おさな馴な染じみなん?」
「違う」
「じゃあ友達?」
「多分」
「曖昧な答えやな」
夏紀の言葉に、みぞれは唇を軽く引き結んだ。その眉間に微かに皺が寄ったのを見て、夏紀は少し意外に思った。たまには人間らしい顔もするらしい。
「……希美といられるだけでいい」
「え?」
小さくつぶやかれた言葉を、夏紀の耳はしっかりと掬すくい上げてしまった。目を伏せたまま、みぞれは静かに首を横に振る。
「なんでもない」
「低音王国……田中あすかの縄張りねぇ」
現在の吹奏楽部は七十人ほど部員が在籍しているが、集団の定めなのか、思惑があちこちで錯さく綜そうしている。現状維持を掲げる三年生、改革を求める一年生、そして板挟みの二年生。
南中の吹奏楽部の三年間。積み重ねられた思い出を、この場で夏紀一人だけが共有していなかった。
嫌だ。嫌だ。
まだ五月。だけど、もう五月だ。
「でも北宇治は去年も府大会で銅賞だったって聞きましたけど」
希美からの受け売りをそっくりそのまま伝えると、香織はどこか困ったように眉尻を下げた。その指が、トランペットのピストンを戯れのように押している。
「うちの部はコンクールで結果を出すことが目標なんじゃなくて、出ることそのものが目標なの。コンクールのA部門には人数制限があって、北宇治は毎年学年順にメンバーが選ばれる。三年生は確実に出られるから、そこで思い出を作るって感じかな」
──集団ってのはパンドラの箱。
そして夏休みになった最初の週、コンクールの準備が始まりつつあるその時期に、一年生と三年生の亀裂は決定的なものとなった。
顧問はその場にいなかったが、夏紀は北宇治ではそういうものだと教えられていたから違和感を抱くことすらなかった。
裏で彼女たちをかばおうとしてくれた二年生たちがいたことは知っている。香織もいろいろと動いてくれたようだが、なんの力にもならなかった。
もしも菫たちが部活を辞めたら、希美と優子と夏紀だけでこの通学路を歩くのだろうか。頭に浮かんだ光景があまりに寒々しく、身体が勝手に身震いした。
そこにみぞれの居場所がないことなんて、すっかり頭から抜け落ちていた。
「サボり魔の夏紀サンの居場所を同じ一年生が教えてくれて」
「アイツらか」
同じ低音パートの一年生二人の顔を思い出し、夏紀は小さく舌打ちした。金管楽器で最大サイズを誇るチューバ担当の彼らは真面目で穏やかで、いかにも低音パートの人間という性格をしていた。
//首次提到老夫老妻ry
「うちはさ、希美がやりたいようにやればいいと思う」
半端に上げた手を動かして、希美の背を軽く叩く。白い夏服越しに、彼女の肩甲骨の感触が伝わった。
「希美自身が信じた選択が、多分、いちばん正しい」
そう言って希美の背を押したのは、間違いなく夏紀だった。右の手のひらの感触を、夏紀は昨日のことのように覚えている。普段は快活な笑顔を浮かべる希美が、その瞬間だけ瞼を下ろした。あふれ出る感情を隠すように、彼女は目を閉じたまま「ありがとう」とつぶやいた。噛み締めるような、小さな声だった。
いまこの瞬間に希美が笑ってくれるなら、それだけでいいと思った。
そしてそれこそが、夏紀の犯した罪だった。
「お前ら性格ブスやなー」
この人が群れのボスなのだと明確に感じ取れる振る舞いだった。
ボス役
先輩たちがあすかの姿を認めた瞬間、室内の空気が一気に変わった。三年生は露骨に顔をしかめ、「田中か」と短くうなった。
雑魚の集まりみたいな三年生よりも、あすかのほうがよっぽど怖い。
「『私』は嫌い、が正しい日本語でしょうに。でも、自分なんかの台詞じゃ夏紀に届かないと卑下して、主語を『みんな』にしはったんでしょう? 先輩のそういう奥ゆかしいところ、めっちゃ勉強になりますわぁ」
//明日香太强了......
「うちが辞めたら、希美の誘いがなかったことになるやんか」
ずるり。四つに区切られた心臓の小部屋から、無自覚に抱き続けていた本音が漏れた。優子は双眸を目一杯開き、こちらの顔を探るように凝視する。
「なかったことにはならんやろ。ってか、希美は夏紀が部活を辞めても気にしいひんと思うし」
「そういうんじゃなくて、うちが嫌。希美の影響を受けた自分をなくしたくないというか」
「ふうん」
「何」
「いや、似てるところもあるんかもしれんなって」
//みぞれ继续部活是因为乐器是她和离开的希美唯一の繋がり
「希美がいない吹奏楽部にいまでもみぞれがすがりついてるのは、昔の希美が『吹奏楽部に一緒に入ろう』って言ったから。みぞれにとって、希美がすべての行動指針なの」
「いやいや、さすがにそれは重すぎない?」
「重いとか軽いとか関係ない。みぞれはそうなの、中学のころから」
そう語気を荒らげる優子の怒りは、いったい誰に向けてのものなのだろう。他人に人生の指針を委ねてしまうみぞれか、感情のベクトルを向けられていることに無自覚な希美か、それとも力になれない自分自身か。
「うちは、一度大事やと思った人間を中途半端に手放したりなんて絶対にしない。香織先輩も、みぞれも」
「香織先輩はそもそもアンタのもんじゃないでしょうが」
「うっさいな、これは心の持ちようなの!」
「うちの大事な人になりたいんやろ?」
「いやべつに」
「いまなら初回サービスでポイント十倍!」
//wwwwww
教えるような腕なんてなかったくせに、その日から、優子と夏紀の吹奏楽部とは無関係のもうひとつの交流が始まったのだった。
夏紀の長い回想を打ち切ったのは、馬のいななきのようなエレキギターの音色だった。
夏紀の腕のなかに納まっているギターはヤマハのパシフィカ112Ⅴ、カラーはオールドバイオリンサンバースト。艶やかなダークブラウンは縁に近づくほど黒みを増す。年上の従姉から譲ってもらった、夏紀の初めてのエレキギターだ。
そして夏紀の隣に座っている優子が構えているのは、同じ型番のギターの色違いだった。彼女が使っているのはヴィンテージホワイト。同じ形をしたギターでも、アイボリーをメインカラーとしたデザインだ。
優子がこのギターを買ったのは、あの夏のあとだ。二人で一緒に楽器屋に行った。いま思うと、二人きりで出かけたのはあれが初めてだった。
夏紀がギターを始めたのは中学二年生のときだ。大学でバンドを組んでいた従姉が、就職を機に新しいのを買うからとそれまで使っていたギターをくれた。従姉がアコースティックギターではなくエレキギターを買ったのは、防音対策がしっかりされていない部屋でもヘッドホンを使って練習できるのが理由らしい。
「卒業ソングなぁ、昔からあんま好きちゃう」
「夏紀はひねくれてるからな」
「シンプルに共感できひんねん、いいこと言ってる歌は」
「悪いことだけが真実ってワケでもないでしょ。悪意は本心に見えやすいだけ」
「さすが部長、ええこと言いますわ」
そう、夏紀は燃え尽きたのだ。いまでもユーフォは好きだし、吹奏楽部も好き。だけどそれ以上に、もうあんなふうに一生懸命頑張りたくない。疲れたから。
「部長は軽音楽に浮気ですか」
「浮気じゃなくて、どっちも本命なの」
低音パートには、強豪校出身のひとつ下の後輩がいた。彼女が担当していたのは、吹奏楽部で唯一の弦楽器であるコントラバスだった。小柄な彼女に不似合いな、全長二メートルほどもある楽器だ。だが、そんな体格差をものともせず、後輩は無邪気に笑いながら演奏の腕前を披露した。すさまじかった。圧倒的だった。
そんなあの子が演奏会でギターを弾いたとき、正直言ってゾッとした。同じ弦楽器だからという理由で、コントラバスの子はギターを担当させられやすい。後輩は「中学のころもよく弾かされました」と笑いながら、平然と難度の高い譜面を弾いていた。
//来来动画做个小绿弹吉他
「うち、最新曲は結構好き」
画面を指差しながら、優子が屈託なく告げる。本当に趣味が正反対だな、と夏紀は思わず苦笑した。
結局この日、夏紀と優子は開店した十時からフリータイムが終わる十九時までカラオケ店に居座った。価格が安いため
「希美は最後までギターやらんかったな」
夏紀のつぶやきに、優子が「フルートひと筋やし」とどこか拗すねるように言った。これまでもギターを始めないかと優子が何度か声をかけたことがあったが、そのたびに希美は断っていた。誰彼構わず優しくするように見せて、意外と頑固なところがあるのだ。
『レチクル』とは菫たちが結成したインストバンドの名前だ。吹奏楽部を辞めた五人で結成したため、ドラム、キーボード、トランペット、サックス、トロンボーンという編成だ。演奏するのはもっぱらジャズで、校外のイベントなんかにも出演している。
//网罟座 Reticulum
//第二次世界大戦末期から1960年までは、一時期小網(こあみ)座と呼ばれた。アン・マキャフリイの『歌う船』に収録されている作品『あざむいた船』にも、「小網座の俗謡を歌う」と訳されたところがある。
先ほど途切れた回想の続きは、バッドエンドでもありハッピーエンドでもあった。
もしも希美が部活を辞めなければ、きっと未来は変わっていただろう。最初から部の中枢に食い込み、その才覚を遺憾なく発揮していたはずだ。部長だって、優子ではなく希美が務めていたかもしれない。それを補佐する副部長の優子の姿を思い浮かべると、自分の想像力の豊かさを恨みたくなるぐらいには様になっていた。
三年生になって希美がコンクールメンバーになっても、関西大会で結果を出しても、夏紀の心の根深いところには罪悪感が巣くっている。
だってあのとき、希美の背を押したのは間違いなく夏紀なのだ。
部活に残れと言えばよかった。アンタ以上に吹奏楽が好きなやつなんていないよ、となんでもない顔で言えばよかった。だが、すべては過ぎ去った過去の話だ。
背負っているのがユーフォニアムでないという事実が、ほんの少しだけ寂しかった。
第一話 傘木希美はツキがない。
(そういうところも好きだったり)
二月になり、最近は学校に行く回数もめっきり減った。多くの生徒が一般入試を間近に控えるなか、夏紀たち合格組は気楽な時間を過ごしている。
あの日、廊下で待ち構えていた三人に向かってみぞれが放ったのは「受かった」というシンプルなひと言だけだった。優子はなぜか泣き、希美は大人びた笑みをたたえてみぞれの背中をなでた。出遅れた夏紀はとりあえずピースすることにした。みぞれは不思議そうな顔で、それでも同じポーズを返してくれた。
そう告げる優子の両目はいまだに潤んでいた。人気ブランドの花柄のハンカチを口元に押し当て、優子は先ほどから「よかった」を繰り返している。はたから見たらみぞれじゃなくて優子が合格したかのように勘違いするかもしれない。
「入るつもり。コンクールで全国とかも行ってるサークルやし」
「大学でも続けるとか、希美はマジですごい」
「そう? みぞれってばモテそうやん」
「優子と違って?」
「はぁ? うちはモテますけど?」
「確かにアンタは黙ってたら可愛いからなぁ」
「黙ってたらって何よ。二十四時間可愛いでしょうが」
「はいはい」
吹奏楽部のなかには部内カップルが何組か存在していて、くっついたり離れたりと忙しい。夏紀が名前を出した二人は北宇治のベストパートナーと名高いチューバパートのカップルで、ひねくれた夏紀にも辛抱強く付き合ってくれていた。あの二人は多分、数年以内に結婚する。
それまで無言でフルーツを咀嚼していたみぞれが、不思議そうに首を傾げる。首筋に沿って伸びる襟足から、彼女の真っ白な肌がのぞいていた。
「みんなは恋人、欲しいの?」
赤ちゃんってどうやってできるの? みたいな、暴力的な無む垢くが詰まった問いかけだった。
「みぞれに彼氏ができたら寝込むかも」と優子がやけに真面目な顔で言う。本当に寝込みそうだな、とパフェの底からシリアルをかき出しながら夏紀は思った。
//这段讨论恋爱xswl
「しかも空いてるな、二月やし」
「明日は予定あるから無理やけど、明後日ならいいで」
希美の言葉に、みぞれが器用に目だけを輝かせる。目尻から目頭までびっしりと生えた細い睫毛が、彼女の感情を示すようにふるりと震えた。
「うれしい」
薄い唇にのる、微かな笑み。隣にいた希美
その後、「じゃ、また明後日に」と手を振った希美とまだ食べ足りなさそうな顔をしたみぞれを見送り、夏紀と優子はいまだに喫茶店に居座っていた。
「優子の趣味、あんま好きとちゃうもん。可愛すぎるっていうか」
「アンタも人のこと言えないでしょ。ピー音入るような過激な歌とか好きじゃん」
いまから一年前の冬、次の部長は優子だと聞いたとき、それ以外ありえないなと思った。彼女の声には力がある。少し高くて、よく通る。鼓舞するような言葉選びが上手く、根拠のない自信を与えるのが得意だ。優子には煽せん動どう家かの適性がある。いい意味でも悪い意味でも。
「滝先生のせい? それともうちのせい?」
「『せい』ではなく『おかげ』ですかね」
「上手くやられたら困るんや」
「優子は感情的になりやすいけど、意外と他人に気を遣う性格をしてる。自分よりも他人を優先するし、怒る理由も自分より他人。自分のダメージに鈍感すぎる」
吉川優子という人間を夏紀は好意的に思っている。裏表がほとんどないし、竹を割ったような性格をしている。嫌なものは嫌と言い、間違っていると感じたときには行動を起こす。周囲の人間への影響力が強く、気づけば周囲を振り回している。
それとは逆に、鎧塚みぞれの世界は狭かった。そもそも他人をどうこうしようという気概がなく、膨れ上がった自意識に振り回されてばかりいる。みぞれの世界には希美以外の登場人物がほとんどいない。それが気に食わなくてあがいているのが優子で、第三者の距離を保ちながら事態を見守っているのが夏紀だった。
「隠すの上手いで、あの子は」
「みぞれがですか」
「そっちちゃう。優子のほう」
「そうちゃんと思える子は意外と少ないよって話。ほら、うちらの一個上の代の先輩らのこと思い出してみ? 下手くそなくせに本番では目立ちたがってたやろ?」
「アイツらと一緒にするのはやめてください」
「無理無理。あの子は同じ時間を共有してへんから」
「同じ時間?」
「滝先生が来て、いままでの北宇治の常識が無茶苦茶に破壊されていったあの時間。傘木希美は所詮、軌道に乗ってから戻ってきただけのよそ者よ」
雨漏りする家のなかにいるときみたいに、心の内側にヒヤリとした何かが落ちた。耳に触れた瞬間に寒気がする、不愉快な四文字。よそ者。そうか、希美はまだよそ者か。
「あすか先輩は希美のことをよそ者だと思ってるんですか?」
「逆に、思ってへんやつがレアちゃう? 普通に馴染んでるけど、それでも部長や副部長みたいな役職を担えるほど人望あるかって言ったらそれは別問題よ」
「でも、中学のときは──」
「アンタがいま口にしたのが答えでしょ。ここは北宇治高校であって、南中じゃない。よその人間関係を持ち込んで、同じように活躍できると期待するのは無責任や」
時間を共有できなかったことを悔やむのは夏紀の専売特許だったのに、気づけば希美に奪われてしまった。あんな疎外感を、希美には味わわせたくなかったのに。
「部長のこと、支えてやってな」
ズルい人だ、と夏紀は口内で小さく舌打ちした。八割が照れ隠し、残り二割が素直に従うのは癪しやくだなというちょっとした反抗心だった。
初めからわかっていたのだ。それがあすかの頼みなら、夏紀は絶対に断れない。助けてもらったあの夏の日の恩を返せるタイミングを、夏紀はいつだってうかがっていた。
「そうじゃなくて、『アントワープブルー』っていうデビュー曲があんの。バンド名はその曲名からとってる」
時間は四分二十一秒。メンバー二人はいまより五歳ほど若く、野暮ったさが目立つ。
//后文照应
『僕は君になりたかった。
おめでとうって笑顔で言える、優しくて素敵で良い奴に。
僕は君になりたかった。
なりたかったのに。
結局、僕は君のなりそこないなんだ。
太陽とか月だとか 使い古された喩たとえで
勝手に理解した気になってんじゃねぇよ。
君に僕がわかってたまるか。
傲慢で臆病で身勝手な僕を。
期待なんてしたくないんだ、とっとと要らないと言ってくれ。
君の差し伸べる手が僕を永遠に苦しめるんだ。
君は僕を大事にしたい。
僕は僕を大事にしない。
めちゃくちゃに壊してやりたいんだ、今すぐに。
僕は君を。僕は僕を。』
//歌词的共鸣度在后面逐步提升
もしも優子に彼氏ができたら。ふと、四人でいたときに出た話題を思い出し、夏紀は自分の唇を片手で覆った。
きっと優子の恋人はいいやつだ。優子の人間を見る目は確かだから、育ちのいい爽やかな好青年を連れてくるだろう。夏紀にはちっとも理解できないファッションセンスで、夏紀にはちっともいいと思えない善良さで、優子の隣に当たり前の顔をして並ぶのだ。
休日にバーベキューをしたら準備なんかも一緒に手伝ってくれて、きっと面倒な仕事も愚痴ひとつ言わない。目が合った夏紀に向かって少し照れたように微笑む。「いつも優子がお世話になってます」なんて言われたところを想像して、架空の男に勝手にムカつく。何がお世話になってます、だよ。こっちはお前の何倍も優子のことを知っているのに。
架空の彼氏にマウントを取っている自分に気づき、その滑稽さに自嘲する。みぞれや希美に彼氏ができても、やっぱり夏紀はイラッとしてしまうのだろう。みぞれに彼氏ができたら寝込むと言った優子の気持ちがいまは少し理解できる。
「優子の彼氏は絶対髪型がマッシュ」
「なんで急に妄想始めたん」
「お洒落眼鏡とか、たまにしてそう」
「あー、そういうギャップは嫌いじゃない。顔は可愛い系がいいかも」
「やっぱりな。勝手に爽やか系イケメンと付き合っとけ」
「情緒不安定なん?」
「髭ひげが生えてそう」「フェスTをパジャマにしてそう」「高いスニーカーをコレクションしてそう」「事あるごとにお金より大事なものがあるって言ってそう」と、さんざんな言い草だ。
そんなみぞれが変わったのはいつのことだっただろう。希美が部に戻ってきてすぐのころは、みぞれは希美の顔を見ないように逃げ回っていた。希美から声をかけられることにおびえ、希美に笑いかけられることにおびえ、希美から優しくされることにおびえ……。それでいて、希美にはそのおびえがちっとも伝わっていなかった。
睫毛に押し込められたみぞれの瞳は、唇よりも雄弁に心情を語る。みぞれが恐れていたのは、希美にとって自分が取るに足らない存在だと思い知らされることだった。
優子はその言葉を優しく受け止め、みぞれの背中をなで、「無理せんでいい」と繰り返した。三人だけの秘密だ。南中出身のメンバーで生き残った、たった三人だけの秘密。
だとしたら報われないなと思う。優子がこれだけ心を砕いても、みぞれを変えられるのは希美だけなのだ。そのくせ、みぞれはそんな自分の状態を希美にだけは絶対に知られたくないと思っている。はたから見たら一目瞭然なのに、自分が秘密にしていればバレないと信じている。その無垢さが、夏紀の目にはひどく傲慢なものに映った。
だって、そこには希美の意思が欠落している。みぞれの想いはいつも一方的で、自己完結していた。希美は自分を傷つけると思ってるくせに、自分は希美を傷つけるほどの影響力がないと勝手に悟ったつもりでいる。
馬鹿じゃないのか。希美だって、ただの人間なのに。
あまりに快活な、翳かげりのない声だった。後ろめたさなんて微塵も感じさせない、ただの友達に対する答え。
気づいていないフリを希美が続けるなら、夏紀だってそれに付き合う。
優子がみぞれの味方になるなら、夏紀は希美の味方になるべきだ。
「あの子が自分なんてって卑下しちゃうのは、結局は自己肯定感が低いからなのよ。いまはそこそこマシになったけどね。後輩ができた影響も大きかったかな」
「後輩は可愛いからな」
「実体験?」
「ノーコメント」
「優子はほんま、みぞれのこと好きやな」
「好きやで。練習熱心でいい子やもん。しかもオーボエがえげつなく上手い。あんな才能あふれた子を前にしたら、誰だってダメになるのはもったいないって本能レベルで思うでしょ」
「思うかぁ?」
「夏紀も多分やられてるって。うちがいるからなんとなく抵抗してるだけで、二人きりになったらコロリよ」
「それだけ聞くと、あの子にある才能は、音楽云うん々ぬんっていうより他人を狂わせる才能やな」
「そのとおりでしょ。希美だって結局は狂わされてたやん」
おそらく、北宇治でもっともソロを経験したのはみぞれだろう。
「嫉妬してるんやろうな」
「八つ当たりしたくなっちゃう自分が嫌になるの。みぞれのこと、ちゃんと好きやのにね。それと同じくらい、多分──」
風が吹いて、希美の声はかき消された。だけど、夏紀はその言葉の続きがたやすく想像できていた。目を伏せ、希美はどこか困ったように笑っている。自分の感情を持て余しているのであろうことは夏紀にはすぐに伝わった。
「そりゃ、友情でしょ」
「あれが?」
「あれも」
だとするなら、友情の定義の範囲は海のように広い。水の入ったグラスを持ち上げ、夏紀はその中身を傾ける。
鎧塚みぞれは、
ふと、無理やりに渡された卒業アルバムのアンケートのことを思い出す。傘木希美にツキがないとするなら、鎧塚みぞれは視野が狭い。
夏紀が大好きな奏法は、アンプをゆがませて行うピックスクラッチだ。巻き弦になっている6弦と5弦の両方にピックを縦に押し当てて、そのままヘッド側にこすり上げる。「ギャイイィン」と耳元でけたたましい音が反響して、それだけで胸がすく思いがする。
鼓膜を揺さぶる音が、夏紀の意識を塗り潰す。理由のない焦燥も、嫌悪も、何もかもがかき消えて、ただ指先の動きにがむしゃらになる。
心の内側の、すっかり燃え尽きて灰になってしまった部分。そこに、小さく何かが芽吹くのを感じる。
今日の最低気温は三度、最高気温は十二度。降水確率はゼロパーセント、絶好の行楽日和だ。
ふふ、と笑ったみぞれの耳には真っ白なイヤーマフが目立っている。吹奏楽部の後輩たちが合格祝いにみぞれへ贈ったプレゼントだ。
「フリーフォール」
「そりゃ、空いてるからって理由で五回も続けて乗ったらそうなるって」
カラカラと笑う夏紀に、優子は信じられないという顔をしている。隣にいるみぞれはケロリとしていて、「もう乗らない?」と未練がましく後ろを振り返っていた。
優子が連続でフリーフォールに乗る羽目になったのは、このみぞれの無邪気なおねだり攻撃のせいだった。みぞれは一度気に入ったものに何度でも乗りたがる。
ちなみにフリーフォールの前には、ジェットコースターと急流すべりにそれぞれ三回ずつ乗っている。
//みぞれ!??太强了吧
最頂部は地上から八十メートル。「頂上からは園内の景色を一望できます!」と書かれた吹き出しの横には、夜と昼の風景差を比較する写真が並んで載っていた。
「夏紀と乗りたい」
「なんでもいい。着られたらそれで」
みぞれの普通は夏紀の普通とは少し違う。
「ギャップがあってええんちゃう。優子が卒倒するかもしれんけど」
B系ファッションに身を包んだみぞれを想像し、夏紀はクハッと弾けるような笑いを漏らした。
もしも夏紀が服を選ぶなら、みぞれをどうコーディネートするだろうか。黒のキャップにぶかぶかの赤のトレーナー、そこからのぞく短い丈のダメージジーンズ。足元はスニーカーがいい、明らかに大きめのやつ。ピアスをしてほしいけれど、みぞれはこれからも耳に穴を開けないだろう。耳にかけるタイプのイヤーカフがいいかもしれない。トカゲとかコウモリの形の、普段ならみぞれが絶対につけないものを選びたい。
それらを身にまとった想像上のみぞれが、キョトンとした顔で自身の袖を引っ張っている。いくら見た目をそれっぽく整えても、内面からにじみ出るみぞれの善良さは隠し切れない。
「わかる。どんな色でも夏紀だから」
「みぞれは人たらしやなぁ」
「夏紀は夏紀」
なんとなくみぞれは南中のメンバーに仲間外れにされていたような気がしていたけれど、それは夏紀の思い込みだったのかもしれない。
「フランスの天文学者のラカーユが、実験道具から名前をとった」
「へぇ、詳しいやん」
「希美が教えてくれたから」
──集中しているとき?
だって、怒ればいいのに。口汚く罵ればいいのに。
それはいまもそうだ。希美の味方は夏紀で、みぞれの味方は優子。そんな配役が自然と続いてしまっている。
「私にとって夏紀はいい人だから。それ以外に何が大事?」
光が灯ともらなくとも、夏紀はその光景を美しいと思う。目の前にいる相手も、もしかすると夏紀と同じ感性を持っているのかもしれない。
「みぞれはさ、希美のことどう思ってる?」
「友達」
即答だった。迷いのない答えに夏紀はたじろぐ。
「希美のこと好き?」
「好き」
「嫌になったりしたことない?」
「希美を?」
「そう、希美を」
「ない」
「一度も?」
「一度も」
「でも」
続いた台詞に、夏紀はハッと顔を上げる。一音一音を吟味するように、みぞれは句切るように言葉を紡いだ。
「希美を好きな自分は嫌いだった」
「希美は悪くないのに、勝手に苦しくなるから」
「それって、恋とは何が違うん?」
「そうだったらよかったのに」
地上から八十メートル。園内でもっとも空に近い場所で、みぞれは驚くほど静かに本音をさらした。
「付き合いたいとか結婚したいとか、そういう感情だったら諦めきれたから」
「諦めるって何を」
「希美を」
人差し指と中指。自分の指がぎこちなく震えたのが、やけに明瞭に感じられた。口内にどんどんとたまる唾を飲み込み、夏紀は正面からみぞれを見つめようと意識的に瞬きをこらえた。
みぞれの表情は穏やかだった。嵐が過ぎ去ったあとのような、傷痕が残る晴れやかさだった。
「ただ、一緒にいたかっただけ。でも、それがいちばん難しい。人間は、理由もなく一緒にはいない」
「理由っていうのは、恋人とか友達とか?」
「学校とか部活とか」
つけ足された内容は、夏紀が挙げたものに比べて他人行儀だった。そんなものを理由と呼ぶのか。夏紀たちがみぞれと一緒にいる理由も、彼女のなかではそうしたものに分類されてしまうのか。それは腹立たしい。夏紀はみぞれだからこうしていまも一緒にいるのに。
「だからさ、うちがいいやつのフリできるのはみぞれのおかげってこと」
「私も好き。高いところが好き。空を飛びたい」
もしも自分の背中から翼が生えたって、夏紀はきっと空を飛べない。屋上の柵にもたれかかって、脚を伸ばして、それで終わりだ。だが、みぞれは違うのだろう。彼女はためらいなく空へと飛び込む。自分が落ちるところを想像すらしないし、皆の心配をよそに、器用に飛んでみせるのだろう。
みぞれが空を飛べるとするなら、希美はどうなのだろうか。ともに空を飛ぶのか、夏紀と同じように屋上から飛び立つみぞれを眺めるだけなのか。
みぞれの背中から真っ白な翼が生えているところを想像する。白鳥みたいな立派な翼だ。傷ひとつなく、力強く羽ばたくことのできる翼。それに違和感がないことに、なぜだか少しゾッとした。自分はみぞれをなんだと思っているのだろう。
「また来たい、みんなで」
みぞれの爪先が、コツンと分厚い壁を叩く。彼女の白いブーツの底は確かにゴンドラの床に着いていた。強張っていた肩の筋肉が、音もなく解けていくのを感じる。夏紀は無意識に頬を緩めた。
「何度だって来たらええやん。友達なんやから」
「友達」
おうむ返しにされた言葉に、夏紀は「そーそー」とうなずいた。人差し指と中指。右手と左手でピースを作り、それを胸の前でくっつける。
「四人は友達」
みぞれはこちらを凝視していたが、やがておずおずと同じポーズを真似してみせた。狭いゴンドラ内に流れる沈黙。冷やかされることを前提としたコミュニケーションは、こういうときに恥ずかしさで身体の内側から爆発しそうになる。
くすぐったそうに身をよじらせ、みぞれは口元を綻ばせる。
「やっぱり、観覧車が好き」
そのままみぞれは空いている希美の隣へ腰かける。夏紀とみぞれで優子と希美を挟んで座るかたちだ。
「でもあれやんな、みぞれって確か中学のとき、吹奏楽部の合宿で優勝してたよな。肝試し大会」
「ベストタイムやってん。そう、確かあれ、お化けにまったく気づいてへんかってさ。優子なんか大騒ぎやったのに」
懐古的な空気になると、途端に夏紀だけが締め出される。無自覚に発生する疎外感にはとっくに慣れてしまった。
「私、ポップコーンが食べたい。しょっぱいの」
「おお、みぞれが希望を言うやなんて……。いますぐ行こう。バター醤しよう油ゆ味のやつが近くで売ってたから」
//第2话开篇插图

優子の手が夏紀の背を軽く叩く。休日だという理由で、今日の彼女の爪先は薄い水色のマニキュアで彩られている。部活時代だとありえないチョイスだ。部長としての優子はきちんと規律を守るほうだったから。
「いや、うちっていうよりみぞれが一方的にな? で、希美やったらどうするかなと思って」
「何が?」
「もしも自分の背中に羽根が生えたらさ、空を飛ぼうって思う?」
「羽根の形状による。サイズとか材質とか」
「えー、そういうこと気にしちゃう?」
「いちばん大事ちゃう? 信頼できないものに命はかけられんやんか。蝶ちようとかトンボの羽根やったら信頼できひんな、コウモリもちょっと怖いかも。鳥もなぁ、あんなもんでほんまに空飛べるか? ってなると思う」
//夏纪是个很现实的人 但这本看完觉得希美更加现实到无情 从选择北宇治完全不考虑社团因素和南中友人的因素 到这个答非所问钻牛角尖到羽翅规格材质的角度 实在是....
「じゃ、どんな羽根なら信頼できる?」
「結局どんなのでも嫌かも。自分の足がいちばん信頼できる」
「つまり、空は飛ばないってことね」
「みぞれは飛びそう」
「あー、やっぱ希美もそう思う?」
「飛べへんかもしれんって思いつきもしなさそう。優子も飛ぶタイプやと思う。あの子はガチガチに地上で練習してから、満を持して空を飛ぶタイプ。で、夏紀に『いまどき地面歩くとかダッサ』とか言うてくる」
「そんな喧嘩売られたらムカつくからうちも飛ぶわ」
「夏紀はさ、優子となら空を飛べるタイプやな」
「そういやここの遊園地、バンジージャンプもあったで」
「やらんからな」
「冗談やん」
//刚想说玩垂直升降不如蹦极....
「部活ロスや、お互い」
「変わったやん。四人のなかでいちばん変わったのが夏紀やと思うわ」
「なぁ、バンド名はどうするん?」
「まだ決めてない」
希美の隣で、夏紀はわざと大股に前進する。バンド名は決まってない。これからの予定も、その先の未来だって、まだなんにも決まってない。
第二話 鎧塚みぞれは視野がせまい。
(それこそが彼女の彼女たる理由)
自室に飾られた木製フレームには、先日の遊園地で撮影した写真が納まっている。イルミネーションで彩られた園内の風景をバックに、四人はレンズに笑顔を向けていた。近くを歩いていたスタッフにお願いして撮影したものだ。
冬は嫌いじゃない。冷たさと痛さは似ていて、浸っていると心地いい。
二月も半ばを過ぎ、登校する機会も残りわずかとなった。あと二週間後には卒業式を迎え、夏紀たちは北宇治高校の生徒ではなくなる。それが寂しいのか、どうでもいいのか、清々するのか。自分の気持ちであるはずなのに、声に出せばどれもが本心からほど遠いものに感じた。
アントワープとはベルギーの北西部にある州都のこと。アントウェルペン、アンベールとも呼ばれる。この都市で使用されていたことがアントワープブルーの名前の由来らしい。
//安特卫普(荷兰语:Antwerpen;德语:Antorf;法语:Anvers)是比利时最重要的商业中心、港口城市和佛兰德的首府,或译为央凡尔(法语)。via中文维基
「店がルミナリエみたいになるーって」
ルミナリエとは「神戸ルミナリエ」、毎年十二月になると神戸市の旧居留地で行われる祭典のことを指す。阪神・淡路大震災の犠牲者への鎮魂と都市の復興への願いを込めて平成七年から開催されている。ルミナリエという言葉はイタリア語でイルミネーションという意味で、その名のとおり、期間中は街がきらびやかな電飾で飾りつけられる。
「みぞれの家って金持ちやしなぁ」
実際に家に行ったことはないが、なんとなく想像はできる。なんせ、家にグランドピアノがある環境だ。夏紀の家のような平凡を絵に描いたような家庭とは大違いだろう。クリスマスのイルミネーションだってとんでもないのかもしれない。
「どこに買いに行く?」
「四条でええんちゃう?」
中世古香織といえば、優子が傾倒していたトランペットパートのひとつ上の先輩だ。卒業したいまは看護学校に進学した。
「そりゃ香織先輩はずっと見目麗しいけど、そういうことじゃなくて、中身が違ったというかさ。もう高校生じゃなかった。大人やった。それがなんか、寂しいなって」
「一つひとつの当たり前に、さよならしてるような気分」
「さよならアントワープブルー」
結果を求められない演奏というのは、なんだか不思議な感じがする。吹奏楽部では自分のミスが全部員の連帯責任となって跳ね返ってきたけれど、ツーピースバンドだと自分のミスはたった二人だけのものだ。
優子とカラオケ店で練習した日からまだ三日もたっていない。おおかた、優子が勝手に夏紀のスケジュールを希美に伝えたのだろう。どうせこの時期は暇だから、予定が埋まるのはありがたいっちゃありがたい。
三月になればほぼすべての入試が終わるため、一気に予定が埋まってしまう。吹奏楽部の三年生で卒業旅行にも行くし、クラスの友達とも出かけなければいけないし、時間も金もすぐに足りなくなる。だから、時間を持て余すなんて贅ぜい沢たくなことができるのはいまだけだ。
希美と優子は夏紀と似たような格好だったが、みぞれだけは違った。彼女が着ているセーターは、いまだかつて見たことがないくらいダサかった。顔だけの猫が目からビームを出し、ビルを破壊しているイラストが深緑色のセーターの中央にデカデカと描かれている。やけに太いフォントで『ゴゴゴゴゴゴ』と書かれているのもダサさポイントを加点していた。
「みぞれ、そのセーターどうしたん」
「汚れてもいい服があるかお母さんに聞いたら、これを出してくれた」
//这啥衣服wwwwwww快映像化
「髪型が違っても、夏紀」
「夏紀ってさ、みぞれの扱い上手いよな」
「普通や普通」
「みぞれ、飴ちゃんあげるからこっちおいで」
「優子はみぞれをなんやと思ってるんや」
いつの間にか夏紀の隣に立っていた希美が、ポンとこちらの背を叩いた。ダウンジャケットの上から彼女が背負うリュックサックはやけに大きく、これから登山にでも行くのかと錯覚しそうになる。
希美がリュックサックから取り出したのは、二メートル四方のブルーシートだった。すでにペンキがこびりついているところを見るに、これまで何度か使ったことのある代物なのだろう。四人で協力して広げ、飛んでいかないように四隅には重石を置く。その上に希美が広げたのは、長方形の形をした真っ白な布だった。縦一メートル、横一・五メートルのそこそこ大きな布だ。
「これ、水性塗料やから」と希美が笑いながら言った。同じペンキでも水性と油性で違いがあるらしい。
缶の中身をのぞき込みながら、優子が感心したようにつぶやく。液体の青は、スマホの画面で見たときよりもずっと暗い色をしていた。銀色の缶のなかに、真夜中の海が沈んでいる。濃縮された青ってこんな色なのか、と夏紀は呑気に考える。青というよりも黒と呼んだほうがいい気がする。
//灰暗色调和各个心情 大会结果 情绪相互照应
その青は、狂おしいくらいに自由だった。
狭苦しいペンキ缶のなかに押し込められていたときとは比べものにならないほど、透き通っていて明るい。徹夜したときに窓から見える日の出前の朝の空気みたいな、澄んだ光をはらんでいる。
//然后预示光明的未来
希美が満足そうにうなずく。それを眺めていたみぞれが、大胆な手つきで布を塗った。慎重に細かく色を埋めていく優子とは対照的に、みぞれは右から左へと刷毛にのったペンキが続く限り塗り進めていく。そのくせ、塗り跡はみぞれのほうが綺麗に仕上がっているのだからすごい。ある種の才能かもしれない。
//みぞれ怎么干啥都厉害doge
一枚の布をすべて青く塗りたくるのには、結局一時間ほどかかった。
「夜になる前の空みたい」と足裏をタオルで拭いながら希美が告げ、
「海の底に似てる」とみぞれは静かにつぶやく。
「夏紀がよく着てるデニムってこんな色ちゃう?」と優子がこちらを見ながら言い、
「情緒がないな」と夏紀は笑った。
自分にはこの青色が何に見えるだろうか。目を凝らしてみると、濃い青と薄い青が重なり合っているのがわかる。氷の下に眠る海? 宇宙が始まる一秒前? 探るうちに思考が詩的になってしまって、夏紀は口をつぐんだ。
ただそこにあるだけで綺麗な色だと思った。
//后文照应
あいこが続くこと三回、四回目のジャンケンでようやく優子とみぞれが近くのスーパーに買い出しに行くことが決定した。
罪滅ぼし。その言葉を、夏紀が希美に告げることは永遠にないだろう。あの日、希美の背中を押した後悔は、自分が抱えるべきものだった。誰にも奪われたくない。たとえその相手が希美であっても。
「そんなんあったっけ。あなたにとってあなた自身の印象は? とかそういう質問しか覚えてない」
「夏紀はなんて書いたん?」
「そもそも回答してない。希美は?」
「うちは、ポジティブ器用貧乏って書いたな」
「いい声やな」
シンプルな称賛に、夏紀は照れをごまかすように頬をかく。「そうやろ」と当然の顔で肯定するには、夏紀の面の皮の厚さが少しばかり足りなかった。
名案だろうと言わんばかりに、優子が気の強そうな両目をこちらに向ける。最後に行った身体測定では夏紀と優子の身長はぴったり同じだったから、こうして向かい合うと目線だって同じになる。
吉川優子という女は、台風の目みたいなやつだった。初めて出会ったころからずっとそうだ。コイツはどこにいたって多くの人間を惹きつけ、巻き込んで、いろいろなものを引っかき回す。
そして夏紀たちが三年生になったとき、北宇治は強豪校としてのシステムを完成させつつあった。
「希美たちが部活を辞めたときにね、トランペットだけっていうのは怖いなって思った」
「怖いって?」
「たとえばさ、トランペットでは絶対に負けたくないって思っちゃったら、それを吹く場所をなくしたときのダメージすごいやん? 希美はフルートやからマイ楽器を持ってたけどさ、じゃあうちがもしチューバパートの人間やったら、部活を辞めることはそのままイコールでチューバを辞めることになっちゃうやん。部活で使う楽器は学校の持ち物やから」
「うちはトランペットやったからマイ楽器って選択肢もあるにはあってんけど、でも、頼るものを分散化しようと思ったの。いろんなものを好きになって、いろんなものを居場所にして……。そうしたら、何かを続けられなくなったときに別の何かが自分を助けてくれるやろ? だからさ、ギターをやりたいなって」
大学生になったら、夏紀と優子はどうなるのだろう。部活という理由がなくなり、授業という枠もほとんどなくなったいま、毎日顔を合わせる必要なんてなくなった。それでもいまもなお二人を密接につないでくれているものは、演奏発表という終わりの存在するイベントだった。
吉川優子の円滑な部活運営は、部長が彼女でなければ成立しない。
//部活運営術ry 传承下去的黄前流人心掌握术
あすかが夏紀を副部長として指名したのも、こうした流れになることを見越してのことだろう。あすかが卒業しても、夏紀はずっと彼女の手のひらの上で踊らされ続けている。
ジャージにTシャツ。今日の夏紀はラフな格好をしている。前にいる優子も似たような服装だ。黒地のTシャツの胸元には、『I must be cruel, only to be kind』と紫色の英文が印刷されていた。
そういえば、と夏紀が自分のTシャツを見下ろすと、セピアカラーの遊園地の写真の上に『Love, the itch, and a cough cannot be hid』とピンク字の英文が躍っていた。意味は知らない。そもそも夏紀は服を買うときに英文の内容を気にしたりはしなかった。たまにとんでもない意味だったりすることがあるので、本当は注意したほうがいいのだろうけど。
「あ、頭をなでてやろうか」
思いついたことをそのまま口に出せば、優子は「いらん」と即答した。その割に彼女の前頭が重そうに傾いていたものだから、夏紀は手を伸ばすことにした。優子の後頭部に手を添え、そのまま抱き込むように小さな頭を肩口に引き寄せる。あれだけ憎まれ口を叩いていたくせに、優子は抵抗しなかった。
夏紀の肩に、彼女の両目が押しつけられる。熱の塊を、Tシャツ越しに意識する。
「……疲れた」
本当は夏紀にだってわかっている。夏紀がいなくたって、優子は自分の感情に折り合いをつけられる。そういう術を知っているやつだ。だからこれは、夏紀の自己満足なのだ。優子の部長としての仮面をバリバリと剥がし取って、破壊し尽くして、それでもって彼女が内に秘めたもろい部分を無理やりに引きずり出してやる。
//很久丽ry
なんでそんなことをするのかと聞かれたら、ムカつくからと夏紀は答える。二年生のときには剥き出しだったはずのそれが、部長に就任した途端に完璧に隠されるだなんて腹立たしい。
泣いてしまえ。
そう口に出してしまえば、優子の涙は自分の前から失われてしまうだろう。なんせ彼女はひどい天あまの邪じや鬼くだから、優しく甘やかしたところで素直になったりしないのだ。
そして、その事実に救われることも。
「もう大丈夫」
優子の手が、夏紀の鎖骨辺りを軽く押す。立ち上がる彼女は憑つき物が落ちたような、どこか晴れやかな表情を浮かべていた。「そっか」と夏紀はうなずく。それ以上の言葉は互いに必要としていなかった。
//为没有人看见这一幕而不用感到害羞 也为没有人看到优子软弱一面而得以维持下去
何か英文が書かれていたことは覚えているのに、それがどんな内容かまではすっかり忘れてしまっている。夏紀の脳内に収納された記憶というのはたいていそうで、どこか細かいところが欠けている。
アコースティックギターとエレキギターじゃ、そのまま弾いたときの音が全然違う。アコースティックギターはボディー内が空洞だからよく音が響くし、エレキギターは中身が詰まったままなので弦だけの響きになる。
だけど夏紀は、こうして密やかに鳴り響くエレキギターの旋律も好きだった。
「卒業証書、授与」
卒業式の日、天気は快晴だった。
代替品があふれている世の中だ。替えの利かない人間なんてきっといない。
この世界は、夏紀が想像するよりずっと上手くできている。
こちらに証書を差し出す校長にとって、自分なんて取るに足らない存在だろうなとぼんやりと考える。彼は夏紀とほかの生徒を区別していないだろうし、それが悪いことだとは微塵も思わない。だって、世の中ってそういうものだし。
ホームルームを終えてクラスメイトたちに別れを告げたあと、元吹奏楽部員たちは中庭に集められていた。一、二年生にとって今日は休日なのだが、式の手伝いがある吹奏楽部員は強制的に登校させられている。そのため、見送り率がほかの部活よりも高いのだ。
この鳥かごは夏紀だけじゃなく、三年生部員全員に用意されているようだった。
オーボエパートのみぞれは泣いてはおらず、代わりに後輩が人目も憚らずに大泣きしていた。ハンカチを差し出すみぞれの表情は普段よりもどこか柔らかく、先輩らしい振る舞いもできるのだなと夏紀は密かに感心した。
ユーフォニアムパートの後輩たちも、夏紀の卒業を惜しんでくれた。少しひねくれた性格の一年生の目は赤かった。それをからかってやれば、彼女は矛先逸らしとばかりに「久美子先輩なんて、演奏の途中で泣いてましたよ」と隣にいる先輩の恥ずかしいところを暴露した。久美子はごまかすどころか、「お別れだと思うと寂しくて」と目を潤ませ始めた。この二人のやり取りは、どちらが振り回してどちらが振り回されているのかたまにわからなくなるのがおもしろい。
後輩たちとの会話は楽しかった。途中からチューバパートとコントラバスの面々も加わり、改めて低音パートでお別れ会をしようという話も決まった。これが今生の別れでないと確信した後輩たちは、明らかにほっとした様子でほかの三年生に話しかけに行った。夏紀はそれを見送る気でいたのだが、なぜか久美子だけがその場から一向に離れようとしなかった。
おびえる久美子を見ているとムカついたから、自分が不愉快な気分にならないためにフォローした。
「救われたんですよ、私は夏紀先輩に」
それに、できることなら最後までカッコいい先輩のフリをしたいじゃないか。
「そう言ってくれるなら、部活に入った意味があったわ」
その日の夕食は家族で焼き肉を食べに行った。一人三千円の九十分食べ放題コース。かしこまったお祝いなんて中川家らしくないし、夏紀だって望んでいない。
はち切れそうなくらいに腹を膨らませ、夏紀たちは帰宅した。机の上には今日の戦利品がうずたかく積まれている。筒に入れたままの卒業証書、書き込みで余白がなくなった卒業アルバム、後輩からもらった鳥かごアレンジのプリザーブドフラワー、イラストとメッセージであふれた色紙、一人ずつ渡された手紙たち。
そのいちばん上にある封筒をつまみ上げ、夏紀はベッドへと寝転がった。送り主の名前は吉川優子。今朝、一緒に登校した際に押しつけられたものだ。どうせ明日もカラオケ店で会うというのに、手紙だなんて律義なやつだ。
封筒の口はラッパのシールで閉じられている。夏紀はそれを手に取り、蛍光灯の光にかざした。本当は、登校しているときに見てやろうと思っていた。だが、優子が自分のいないときに読めとしつこく念押ししてきたから読むのは後回しにした。
シールを爪先で引っかくと簡単に剥がれた。なかに入っていた便せんは意外と枚数があった。夏紀は身を起こし、ふたつ折りにされた紙を開く。『中川夏紀さま』なんて書き出しから文章は始まっていた。
//第3话开篇插图
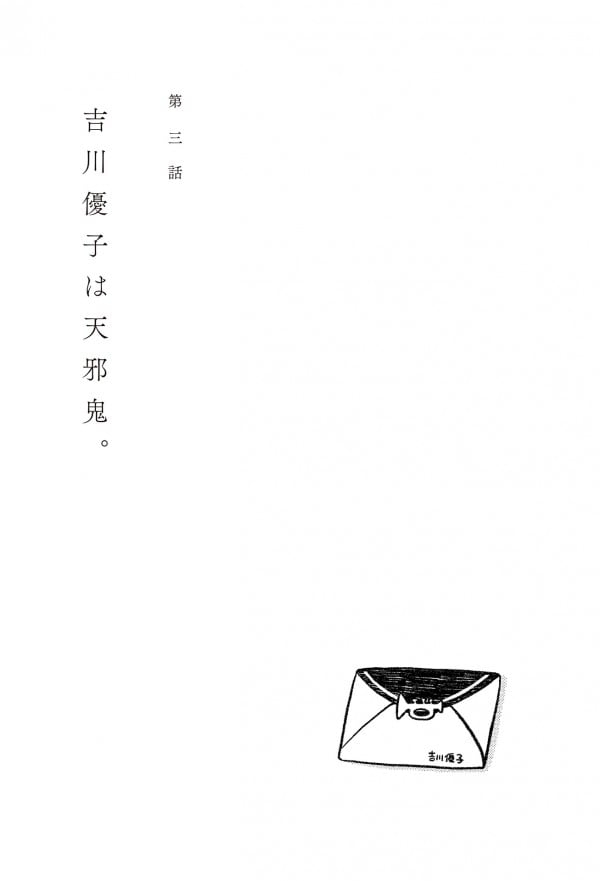 結びは、『やっぱ渡さんほうがええような気がしてきた吉川優子より』なんて彼女らしい言葉だった。夏紀は手紙を手にしたまま、ただ茫ぼう然ぜんと息を吐いた。自身の肺に詰まった空気が、とぷりと震えたような気がした。
結びは、『やっぱ渡さんほうがええような気がしてきた吉川優子より』なんて彼女らしい言葉だった。夏紀は手紙を手にしたまま、ただ茫ぼう然ぜんと息を吐いた。自身の肺に詰まった空気が、とぷりと震えたような気がした。
便せんを再び折り畳み、夏紀は封筒のなかへと戻した。片づける気にはどうしてもならなくて、そのままベッドの隅に置く。
「恥ずかしいやつ」
前に優子と動物映画を見たときは涙を流してしまったし。
今日はもう眠ってしまいたい。イベントの本番まで一週間を切っている。
今日のスケジュールは至ってシンプルだ。十三時から優子とカラオケ店で練習。以上。
せっかく卒業したし、おめかしでもするか。見せる相手は優子だけだがそれでもいい。
使い終わった食器を片づけ、夏紀はいそいそと身支度を始める。パステルピンクのタイトなデニムスカートに、だぼだぼした黒のトレーナー。靴下もスニーカーも鞄も黒に統一しよう。母親から卒業祝いに贈られたメイクボックスを開けて、化粧なんかもやっちゃったりして。
下地を塗って、ファンデーションをして、眉を整えて、アイシャドウやらアイライナーを使って。鏡に映る自分を凝視しながら、オレンジ色のリップを塗る。できあがった自分の顔を見て、なかなかいい仕上がりなんじゃない? とちょっと角度を変えてみる。ふふんと鼻を鳴らして、満足して──そして、すべてがどうでもよくなった。
これが燃え尽き症候群ってやつですか?
べつに、寂しいわけじゃない。悲しいわけでもない。ただ、虚むなしい。あれだけ濃密な時間をともにしたというのに、いったい自分に何が残ったというのだろう。すぐ間近にいた人間も、いつの日か思い出のなかの住民になってしまう。音楽室に集まって同じメンバーで合奏することは、これから先、二度とない。
熱い何かが頬を伝って、夏紀は反射的に指で拭った。それが涙であることに気づくのに、数秒のタイムラグがあった。瞬きすると、瞼の縁から押し出されてぼろぼろと涙があふれ出す。いまさらかよ、そうつぶやこうとして唇が震えた。
呼吸のリズムが崩れ、夏紀はソファーの上にあったクッションを抱きしめる。涙腺の蛇口が壊れてしまったのか、涙があふれて止まらない。「バスタオルが必要か?」とイマジナリー優子が揶揄する。必要かもしれないなと夏紀はクッションに額を押しつけながら思った。
ひどくなる嗚咽をこらえようともせず、夏紀はただ泣き続けた。涙の条件は一人になることだったのかと、夏紀はようやく思い知った。
なんせ、彼女は意地でも夏紀の隣に並ぶから。
肩幅に足を開き、夏紀は優子の顔を見やる。コクンとうなずかれ、互いの準備が済んでいることを確認する。メトロノームは使わない。曲のテンポを決めるのは、最初に奏でる四分音符の連続だ。
夏紀の右手が一、二、三、四、とリズムを刻む。その直後、優子のギターが加わってくる。それぞれの担当は、優子がメインメロディーを担うリードギター、歌う夏紀がバッキングだ。
見てみたかった、あの子と同じ世界を。
いななきに似たギターの旋律。優子が夏紀を見る。まっすぐな眼差しが夏紀の両目を頭蓋骨ごと貫いた。よそ見なんて許さないって、幼稚な愛を叫んでいるみたい。
「いや、青がいい。うちがやったげるからさ、アンタの家泊まっていい?」
//突击ry
「ウチのオカン、優子のこと気に入ってるもん。礼儀正しい子やわぁって」
「この前家に遊びに行ったときにちゃんと手土産持っていった甲か斐いがあったな」
//草
優子が夏紀の家に泊まりに来たのは、その三日後だった。
夏紀の自室に入るなり、優子はニヤニヤしながら木製フレームの写真立てを手に取った。遊園地に行って、四人で撮ったときの写真だ。
「なんかさ、演奏会が終わったらほんまに卒業やなって気がせん?」
グラスを傾けながら、優子がしんみりとつぶやく。
「卒業式はもう終わったやん」
「そうやねんけど、演奏会があるうちはまだ高校生活の延長って感じもあったっていうか、さ。ほんまに……ほんまに、終わるんやなって思う」
「何が」
「うちの高校生活が」
「正直なこと言うてさ、うち、みぞれのこともちょっと苦手やった。だってあの子、自分の振る舞いが希美の目にどう映ってるか、全然気づいてないんやもん。苛つくやんか、そんなん。なのにあの子、うちに平気で言うねん。『夏紀はいい人』って」
ずっと、許せないのだ。あの日、希美の背中を押した自分自身を。皆が空気を読んで駆け出したとき、遠くから冷笑した自分自身を。だから夏紀の優しく見える振る舞いは、すべてが罪滅ぼしなのだ。誰かの一生懸命を馬鹿にしていた、あのころの自分を許せないだけ。
「アンタがどう思ってるかなんて、それこそどうでもいいっての。優しくされたほうはうれしくて助かって、頑張る理由になった。だからアンタに感謝してるの。こっちの感謝をねじ曲げようやなんて、それこそ身勝手な理屈やな」
「いくらでも代わりがいるなかで、うちはアンタを選んでこうやって一緒にいるワケ。代わりがないからじゃなくて、代わりがいくらあってもアンタを選ぶ。一緒に音楽やるのも、こうやって過ごすのも、夏紀と一緒がいいよ。それが悪いこととはうちにはどうしても思えへん」
視界は青かった。夜になる前の空みたいな、海の底にいるみたいな、光をまとった青色が小さな世界を満たしていた。
//照应 哭了
「そんな恥ずかしいこと、堂々とよく言えるな」
「そういう流れだったでしょうが! いま!」
「ま、うちだって選ぶならアンタ以外考えられへんな」
「ソッチのほうが千倍恥ずかしい!」
***
本番当日はあっという間にやってきた。
会場となるカフェは地下にあり、窓は一切なかった。太陽光は差し込まないが、代わりに間接照明を大量に配置することで物々しい雰囲気になることを避けている。
打ちっ放しのコンクリートの壁には電飾ケーブルが飾りつけられており、会場内をほんのりと青く染め上げていた。十五時から十八時まで、今日は夏紀たちによる貸し切りだ。開演は十六時のため、いまは演者と手伝いのスタッフしかいない。
先ほどまで菫との会話に花を咲かせていた希美が、大股でこちらに歩み寄ってくる。それを後ろから追いかけるみぞれの髪型は、珍しくポニーテールだった。
//!!!
コクリと首を縦に振り、みぞれは急にピースサインを作り出した。右手と左手でピースをし、人差し指同士を胸の前でくっつける。
「W?」
「なんのポーズ?」
不思議そうな顔をする希美と優子を無視し、夏紀もまた同じポーズをしてみせた。それを見たみぞれの唇が満足そうに綻ぶ。込められた意味を知っているのは、この場では二人だけだった。
「そういう暗号? 秘密結社みたいやな」とトンチンカンなことを言いながら、希美がみぞれのポーズを真似する。やっていないのは残り一人だ。促す三人の視線を受け、「何このノリ」と唇をとがらせながら、優子がゆっくりと両手でピースサインを作る。
四人は同じポーズで向き合い、誰からともなく笑い出した。本番の開始時刻が、緩やかに迫っていた。
//「四人は友達」
//最后的插图照应

夏紀は優子を見る。そして、優子も夏紀を見る。それだけで準備はもう済んでいた。
マイクに近づく自身の唇が、今日の二人の名前を紡ぐ。
「さよなら、アントワープブルー」
カウント代わりに動くピックが弦を静かにかき鳴らす。
長くて短い、四分二十一秒の歌。
その始まりを告げる爪先は、どこまでも自由な色をしていた。
第三話 吉川優子は天邪鬼。
(そしてそれはお互い様)
エピローグ
金賞と書かれた賞状を掲げ持つ優子は清すが々すがしい笑顔を浮かべていて、その目が赤く腫れていることなんて写真を見ただけじゃ誰も気づかないだろう。胸を張る彼女の姿を、夏紀はいまでも誇らしく思う。その傍らに寄り添うようにして立つ、自分自身の振る舞いも。
ここに写っているのは、部長と副部長しての優子と夏紀だった。
「松本先生が人気だったんだよね」
「うちは絶対滝先生が一位やと思ったけどなぁ」
//所以顺位是怎样
13 あなたの自分自身への印象は?
無意識に伸ばした指が、印刷された文字をたどった。この問いに対する答えを、自分はずっと探し続けていたような気がする。
もしもいま、手元に回答用紙があったならば、夏紀は迷いなくこう書いただろう。
中川夏紀は、身勝手だ。
でも、そんな自分も嫌いじゃない。
减少了肢体描写
可以ctrl+f一下"背" 看武田描写了多少次敲打//推人背 我基本都摘下来了ry

想摘录就摘录了没啥门槛或者标准 这次吐槽比较少
直接复制出来的 注音基本没修见谅
Q5 高校生活の忘れられない思い出は?
Q6 あなたがいちばん好きな先生は?
Q7 将来きっと大物になると思う人物は?
Q12 あなたが友達に抱いている印象は?
Q13 あなたの自分自身への印象は?
値段は確か、百万円近くしたはずだ。吹奏楽部で使用される管楽器のなかでもオーボエはかなり高額な部類に入る。
「世界でいちばん難しい木管楽器」としてギネスブックに登録されていたりする。
「捕まえたら食べられそう」
「何を?」
「光」
「そういやさ、吹部の卒業旅行はどうする? 去年の先輩らはスキー行ったらしいけど」
話題を振った夏紀の左側に希美が、右側に優子が並んで歩く。四人でいるときは前後の列で二人、二人になることが多いけれど、三人のときはこうして一列になる。だが、これがみぞれを含めた三人になると、なぜかみぞれと二人に分かれてしまう。みぞれが浮いているとかそういうわけじゃない。ただ、みぞれは一人になりがちな子だった。
「それでええやん。入試の日程が全部終わった時期がええやろな、三月下旬とか」
面倒なことはさっさと忘れて、楽しかったことだけを覚えていたい。好きなもの、好きな人、それだけに脳のリソースを割きたい。
「みぞれ、あんま歌わんからなー。タンバリンばっか叩たたいてるやんあの子」
全国大会後、三年生だけで行った打ち上げの様子を思い出し、夏紀の口元は自然と緩んだ。
「アントワープブルーね」
アントワープブルーは最近メジャーデビューを果たした四人組ロックバンドだ。
最近では映画の主題歌を担当するなど、活躍がめざましい。
「ネットで買ってダウンロードすればいいのに」
そう告げる希美に、わかってないなと夏紀は首を左右に振る。
「こういうのはちゃんと店で買いたいの。予約して、発売日に受け取る。フィルムを剥がすあのドキドキ感までが一連のイベントなワケよ」
誰かを気にせずに歩くのは好きだ。一人でいるのが好き。だけど、ずっと一人でいるのはちょっとだけ寂しい。
男性ボーカル
昔から、夏紀はパンクやロックといった激しい音楽が好きだった。クラシックみたいなお行儀のいい音楽は退屈だし、自分の肌には合わないと感じていた。だけど、吹奏楽部に入ってからそうしたものへの見方も少し変わった。それがいいことなのか悪いことなのか、自分でもよくわからない。
一月の風が、夏紀の頬に突き刺さる。
頭に立派がつくようなものにはなりたくない、大人にだってなりたくない。
棚に飾られたCDケースのすぐ隣には、後輩たちからもらった写真立てが飾られていた。木製のフレームには、夏紀の好きな熊のマスコットキャラクターが描かれている。
//第1话的开篇插图

夏紀の服の好みは、好きなバンドの影響を大いに受けている。可愛かわいいよりもカッコよくなりたいし、パステルカラーよりはビビッドカラーのほうが好きだ。ダメージジーンズもレザージャケットも大好きだし、髪の毛もいつかは染めたいと思う。
それとは逆に、優子は清せい楚そ系ファッションを好む。吹奏楽部時代の憧れの先輩がそうした格好をしていたせいだ。リボンやフリルのついた服装が好きで、流行の小物をセンスよく取り入れている。
「夏紀は希美派やからしゃあないか」
「じゃ、優子はみぞれ派やな」
「当たり前やん」
「そこ、自分で認めるんや」
「あの子、ずっと一生懸命やったやんか。ああいう子が報われてほしい」
「希美だって一生懸命やったけどね」
「希美とみぞれじゃ、一生懸命の種類が違うやん」
「それはなんとなくわかる」
「でしょ」
中学三年生のとき、夏紀と希美は同じクラスだった。南中は一学年が四クラス
夏紀たちが通っていた南中では、毎年一月の第三木曜日に大縄跳び大会が開催されることになっていた。クラスごとに男女に分かれて大縄を跳び、回数を競い合う。優勝したからといってとくに賞品があるわけでもなく、得られるのは名誉だけだ。
夏紀たちのクラスは学年四クラス中三位という中途半端な結果となった。
夏紀が受験した北宇治高校は、東中出身の子が全校生徒の五割を占める。南中の子も少なくはないが、圧倒的に多いというわけでもない。
「ほかに南中の子はいいひんの? 吹奏楽部の子とか」
「菫すみれは一緒やってんけど、ほかは別のクラスやねんなあ」
「菫? あぁ、若わか井いさんね」
若井菫とは夏紀も中学一年生のときに同じクラスだった。ほとんどしゃべったことはないが、派手な白縁眼鏡が特徴的だったから顔だけはよく覚えている。
「菫はサックスがめちゃくちゃ上手いねん。高校でも一緒に吹奏楽部に入るって約束しててさ」
「夏紀、南中の吹奏楽部員が何人いたか知ってる?」
「知るわけないやん」
「うちが部長だった代で八十三人。うちの学年はとくに多くて三十四人いた。で、例年だと南中の子は三割くらいが北宇治に進学する」
「うち、夏紀はパーカッションとか向いてると思うねんなぁ」
//一开始被认为适合打鼓hhh 确实很搭
「初心者ちゃんは、これやっとけばとりあえず大丈夫」
そう言って夏紀に楽譜を渡してきたひとつ上の先輩──田た中なかあすかは、全学年の部員たちから一目置かれていた。楽器も上手い、頭もいい、さらにはやたらと口が回る。その先輩さえいれば、低音パートには何ひとつ困った問題は起こらなかった。同じ学年の友人たちは優しい性格で、揉もめ事もほとんどなかった。
//来了 明日香天下第一
今年の南中出身の一年生は九人で、夏紀を除いた八人が経験者だった。しかも中学時代に関西大会出場を果たしているだけあって、どの子も演奏が上手い。サボりが当たり前の北宇治の吹奏楽部で、ここにいる夏紀以外の八人が先輩に目をつけられるのは致し方のないことだった。
「はー、副顧問が顧問になってくれたらええのに」
「そんなんしたら今度は三年が暴れ散らして収拾つかんでしょ。ってか、いまの三年は顧問を懐柔することで副顧問に対抗してんねんから。顧問と三年生は、副顧問が口出ししないようにするって方向では利害が一致してる」
北宇治の吹奏楽部の顧問は梨り香か子こ先生という二十代後半の女性教師で、やる気のない三年生部員によく振り回されていた。
副顧問の松まつ本もと先生は五十代のベテラン音楽教師で、とにかく厳しいことで有名だった。本来ならば顧問になるべき存在なのだろうが、家庭の事情で副顧問に収まっているらしい。吹奏楽部にあまり介入しないのは、顧問である梨香子先生に気を遣ってのことだろうという噂うわさもあった。梨香子先生は松本先生がいると露骨に萎縮していたからだ。そんな大人の事情、こちらからすると知ったことではないのだけれど。
南中出身の一年生たちは、梨香子先生を軽蔑していた。
「オーボエに先輩はいない」
「みぞれってさ、なんでオーボエ選んだん?」
問いかけに、みぞれの瞳がそろりと動く。闇色をした瞳に、前を歩く希美の後ろ姿が映り込む。
「希美が言ったから」
「オーボエをやれって?」
「違う。吹奏楽部に入らないかって」
「みぞれと希美は幼おさな馴な染じみなん?」
「違う」
「じゃあ友達?」
「多分」
「曖昧な答えやな」
夏紀の言葉に、みぞれは唇を軽く引き結んだ。その眉間に微かに皺が寄ったのを見て、夏紀は少し意外に思った。たまには人間らしい顔もするらしい。
「……希美といられるだけでいい」
「え?」
小さくつぶやかれた言葉を、夏紀の耳はしっかりと掬すくい上げてしまった。目を伏せたまま、みぞれは静かに首を横に振る。
「なんでもない」
「低音王国……田中あすかの縄張りねぇ」
現在の吹奏楽部は七十人ほど部員が在籍しているが、集団の定めなのか、思惑があちこちで錯さく綜そうしている。現状維持を掲げる三年生、改革を求める一年生、そして板挟みの二年生。
南中の吹奏楽部の三年間。積み重ねられた思い出を、この場で夏紀一人だけが共有していなかった。
嫌だ。嫌だ。
まだ五月。だけど、もう五月だ。
「でも北宇治は去年も府大会で銅賞だったって聞きましたけど」
希美からの受け売りをそっくりそのまま伝えると、香織はどこか困ったように眉尻を下げた。その指が、トランペットのピストンを戯れのように押している。
「うちの部はコンクールで結果を出すことが目標なんじゃなくて、出ることそのものが目標なの。コンクールのA部門には人数制限があって、北宇治は毎年学年順にメンバーが選ばれる。三年生は確実に出られるから、そこで思い出を作るって感じかな」
──集団ってのはパンドラの箱。
そして夏休みになった最初の週、コンクールの準備が始まりつつあるその時期に、一年生と三年生の亀裂は決定的なものとなった。
顧問はその場にいなかったが、夏紀は北宇治ではそういうものだと教えられていたから違和感を抱くことすらなかった。
裏で彼女たちをかばおうとしてくれた二年生たちがいたことは知っている。香織もいろいろと動いてくれたようだが、なんの力にもならなかった。
もしも菫たちが部活を辞めたら、希美と優子と夏紀だけでこの通学路を歩くのだろうか。頭に浮かんだ光景があまりに寒々しく、身体が勝手に身震いした。
そこにみぞれの居場所がないことなんて、すっかり頭から抜け落ちていた。
「サボり魔の夏紀サンの居場所を同じ一年生が教えてくれて」
「アイツらか」
同じ低音パートの一年生二人の顔を思い出し、夏紀は小さく舌打ちした。金管楽器で最大サイズを誇るチューバ担当の彼らは真面目で穏やかで、いかにも低音パートの人間という性格をしていた。
//首次提到老夫老妻ry
「うちはさ、希美がやりたいようにやればいいと思う」
半端に上げた手を動かして、希美の背を軽く叩く。白い夏服越しに、彼女の肩甲骨の感触が伝わった。
「希美自身が信じた選択が、多分、いちばん正しい」
そう言って希美の背を押したのは、間違いなく夏紀だった。右の手のひらの感触を、夏紀は昨日のことのように覚えている。普段は快活な笑顔を浮かべる希美が、その瞬間だけ瞼を下ろした。あふれ出る感情を隠すように、彼女は目を閉じたまま「ありがとう」とつぶやいた。噛み締めるような、小さな声だった。
いまこの瞬間に希美が笑ってくれるなら、それだけでいいと思った。
そしてそれこそが、夏紀の犯した罪だった。
「お前ら性格ブスやなー」
この人が群れのボスなのだと明確に感じ取れる振る舞いだった。
ボス役
先輩たちがあすかの姿を認めた瞬間、室内の空気が一気に変わった。三年生は露骨に顔をしかめ、「田中か」と短くうなった。
雑魚の集まりみたいな三年生よりも、あすかのほうがよっぽど怖い。
「『私』は嫌い、が正しい日本語でしょうに。でも、自分なんかの台詞じゃ夏紀に届かないと卑下して、主語を『みんな』にしはったんでしょう? 先輩のそういう奥ゆかしいところ、めっちゃ勉強になりますわぁ」
//明日香太强了......
「うちが辞めたら、希美の誘いがなかったことになるやんか」
ずるり。四つに区切られた心臓の小部屋から、無自覚に抱き続けていた本音が漏れた。優子は双眸を目一杯開き、こちらの顔を探るように凝視する。
「なかったことにはならんやろ。ってか、希美は夏紀が部活を辞めても気にしいひんと思うし」
「そういうんじゃなくて、うちが嫌。希美の影響を受けた自分をなくしたくないというか」
「ふうん」
「何」
「いや、似てるところもあるんかもしれんなって」
//みぞれ继续部活是因为乐器是她和离开的希美唯一の繋がり
「希美がいない吹奏楽部にいまでもみぞれがすがりついてるのは、昔の希美が『吹奏楽部に一緒に入ろう』って言ったから。みぞれにとって、希美がすべての行動指針なの」
「いやいや、さすがにそれは重すぎない?」
「重いとか軽いとか関係ない。みぞれはそうなの、中学のころから」
そう語気を荒らげる優子の怒りは、いったい誰に向けてのものなのだろう。他人に人生の指針を委ねてしまうみぞれか、感情のベクトルを向けられていることに無自覚な希美か、それとも力になれない自分自身か。
「うちは、一度大事やと思った人間を中途半端に手放したりなんて絶対にしない。香織先輩も、みぞれも」
「香織先輩はそもそもアンタのもんじゃないでしょうが」
「うっさいな、これは心の持ちようなの!」
「うちの大事な人になりたいんやろ?」
「いやべつに」
「いまなら初回サービスでポイント十倍!」
//wwwwww
教えるような腕なんてなかったくせに、その日から、優子と夏紀の吹奏楽部とは無関係のもうひとつの交流が始まったのだった。
夏紀の長い回想を打ち切ったのは、馬のいななきのようなエレキギターの音色だった。
夏紀の腕のなかに納まっているギターはヤマハのパシフィカ112Ⅴ、カラーはオールドバイオリンサンバースト。艶やかなダークブラウンは縁に近づくほど黒みを増す。年上の従姉から譲ってもらった、夏紀の初めてのエレキギターだ。
そして夏紀の隣に座っている優子が構えているのは、同じ型番のギターの色違いだった。彼女が使っているのはヴィンテージホワイト。同じ形をしたギターでも、アイボリーをメインカラーとしたデザインだ。
優子がこのギターを買ったのは、あの夏のあとだ。二人で一緒に楽器屋に行った。いま思うと、二人きりで出かけたのはあれが初めてだった。
夏紀がギターを始めたのは中学二年生のときだ。大学でバンドを組んでいた従姉が、就職を機に新しいのを買うからとそれまで使っていたギターをくれた。従姉がアコースティックギターではなくエレキギターを買ったのは、防音対策がしっかりされていない部屋でもヘッドホンを使って練習できるのが理由らしい。
「卒業ソングなぁ、昔からあんま好きちゃう」
「夏紀はひねくれてるからな」
「シンプルに共感できひんねん、いいこと言ってる歌は」
「悪いことだけが真実ってワケでもないでしょ。悪意は本心に見えやすいだけ」
「さすが部長、ええこと言いますわ」
そう、夏紀は燃え尽きたのだ。いまでもユーフォは好きだし、吹奏楽部も好き。だけどそれ以上に、もうあんなふうに一生懸命頑張りたくない。疲れたから。
「部長は軽音楽に浮気ですか」
「浮気じゃなくて、どっちも本命なの」
低音パートには、強豪校出身のひとつ下の後輩がいた。彼女が担当していたのは、吹奏楽部で唯一の弦楽器であるコントラバスだった。小柄な彼女に不似合いな、全長二メートルほどもある楽器だ。だが、そんな体格差をものともせず、後輩は無邪気に笑いながら演奏の腕前を披露した。すさまじかった。圧倒的だった。
そんなあの子が演奏会でギターを弾いたとき、正直言ってゾッとした。同じ弦楽器だからという理由で、コントラバスの子はギターを担当させられやすい。後輩は「中学のころもよく弾かされました」と笑いながら、平然と難度の高い譜面を弾いていた。
//来来动画做个小绿弹吉他
「うち、最新曲は結構好き」
画面を指差しながら、優子が屈託なく告げる。本当に趣味が正反対だな、と夏紀は思わず苦笑した。
結局この日、夏紀と優子は開店した十時からフリータイムが終わる十九時までカラオケ店に居座った。価格が安いため
「希美は最後までギターやらんかったな」
夏紀のつぶやきに、優子が「フルートひと筋やし」とどこか拗すねるように言った。これまでもギターを始めないかと優子が何度か声をかけたことがあったが、そのたびに希美は断っていた。誰彼構わず優しくするように見せて、意外と頑固なところがあるのだ。
『レチクル』とは菫たちが結成したインストバンドの名前だ。吹奏楽部を辞めた五人で結成したため、ドラム、キーボード、トランペット、サックス、トロンボーンという編成だ。演奏するのはもっぱらジャズで、校外のイベントなんかにも出演している。
//网罟座 Reticulum
//第二次世界大戦末期から1960年までは、一時期小網(こあみ)座と呼ばれた。アン・マキャフリイの『歌う船』に収録されている作品『あざむいた船』にも、「小網座の俗謡を歌う」と訳されたところがある。
先ほど途切れた回想の続きは、バッドエンドでもありハッピーエンドでもあった。
もしも希美が部活を辞めなければ、きっと未来は変わっていただろう。最初から部の中枢に食い込み、その才覚を遺憾なく発揮していたはずだ。部長だって、優子ではなく希美が務めていたかもしれない。それを補佐する副部長の優子の姿を思い浮かべると、自分の想像力の豊かさを恨みたくなるぐらいには様になっていた。
三年生になって希美がコンクールメンバーになっても、関西大会で結果を出しても、夏紀の心の根深いところには罪悪感が巣くっている。
だってあのとき、希美の背を押したのは間違いなく夏紀なのだ。
部活に残れと言えばよかった。アンタ以上に吹奏楽が好きなやつなんていないよ、となんでもない顔で言えばよかった。だが、すべては過ぎ去った過去の話だ。
背負っているのがユーフォニアムでないという事実が、ほんの少しだけ寂しかった。
第一話 傘木希美はツキがない。
(そういうところも好きだったり)
二月になり、最近は学校に行く回数もめっきり減った。多くの生徒が一般入試を間近に控えるなか、夏紀たち合格組は気楽な時間を過ごしている。
あの日、廊下で待ち構えていた三人に向かってみぞれが放ったのは「受かった」というシンプルなひと言だけだった。優子はなぜか泣き、希美は大人びた笑みをたたえてみぞれの背中をなでた。出遅れた夏紀はとりあえずピースすることにした。みぞれは不思議そうな顔で、それでも同じポーズを返してくれた。
そう告げる優子の両目はいまだに潤んでいた。人気ブランドの花柄のハンカチを口元に押し当て、優子は先ほどから「よかった」を繰り返している。はたから見たらみぞれじゃなくて優子が合格したかのように勘違いするかもしれない。
「入るつもり。コンクールで全国とかも行ってるサークルやし」
「大学でも続けるとか、希美はマジですごい」
「そう? みぞれってばモテそうやん」
「優子と違って?」
「はぁ? うちはモテますけど?」
「確かにアンタは黙ってたら可愛いからなぁ」
「黙ってたらって何よ。二十四時間可愛いでしょうが」
「はいはい」
吹奏楽部のなかには部内カップルが何組か存在していて、くっついたり離れたりと忙しい。夏紀が名前を出した二人は北宇治のベストパートナーと名高いチューバパートのカップルで、ひねくれた夏紀にも辛抱強く付き合ってくれていた。あの二人は多分、数年以内に結婚する。
それまで無言でフルーツを咀嚼していたみぞれが、不思議そうに首を傾げる。首筋に沿って伸びる襟足から、彼女の真っ白な肌がのぞいていた。
「みんなは恋人、欲しいの?」
赤ちゃんってどうやってできるの? みたいな、暴力的な無む垢くが詰まった問いかけだった。
「みぞれに彼氏ができたら寝込むかも」と優子がやけに真面目な顔で言う。本当に寝込みそうだな、とパフェの底からシリアルをかき出しながら夏紀は思った。
//这段讨论恋爱xswl
「しかも空いてるな、二月やし」
「明日は予定あるから無理やけど、明後日ならいいで」
希美の言葉に、みぞれが器用に目だけを輝かせる。目尻から目頭までびっしりと生えた細い睫毛が、彼女の感情を示すようにふるりと震えた。
「うれしい」
薄い唇にのる、微かな笑み。隣にいた希美
その後、「じゃ、また明後日に」と手を振った希美とまだ食べ足りなさそうな顔をしたみぞれを見送り、夏紀と優子はいまだに喫茶店に居座っていた。
「優子の趣味、あんま好きとちゃうもん。可愛すぎるっていうか」
「アンタも人のこと言えないでしょ。ピー音入るような過激な歌とか好きじゃん」
いまから一年前の冬、次の部長は優子だと聞いたとき、それ以外ありえないなと思った。彼女の声には力がある。少し高くて、よく通る。鼓舞するような言葉選びが上手く、根拠のない自信を与えるのが得意だ。優子には煽せん動どう家かの適性がある。いい意味でも悪い意味でも。
「滝先生のせい? それともうちのせい?」
「『せい』ではなく『おかげ』ですかね」
「上手くやられたら困るんや」
「優子は感情的になりやすいけど、意外と他人に気を遣う性格をしてる。自分よりも他人を優先するし、怒る理由も自分より他人。自分のダメージに鈍感すぎる」
吉川優子という人間を夏紀は好意的に思っている。裏表がほとんどないし、竹を割ったような性格をしている。嫌なものは嫌と言い、間違っていると感じたときには行動を起こす。周囲の人間への影響力が強く、気づけば周囲を振り回している。
それとは逆に、鎧塚みぞれの世界は狭かった。そもそも他人をどうこうしようという気概がなく、膨れ上がった自意識に振り回されてばかりいる。みぞれの世界には希美以外の登場人物がほとんどいない。それが気に食わなくてあがいているのが優子で、第三者の距離を保ちながら事態を見守っているのが夏紀だった。
「隠すの上手いで、あの子は」
「みぞれがですか」
「そっちちゃう。優子のほう」
「そうちゃんと思える子は意外と少ないよって話。ほら、うちらの一個上の代の先輩らのこと思い出してみ? 下手くそなくせに本番では目立ちたがってたやろ?」
「アイツらと一緒にするのはやめてください」
「無理無理。あの子は同じ時間を共有してへんから」
「同じ時間?」
「滝先生が来て、いままでの北宇治の常識が無茶苦茶に破壊されていったあの時間。傘木希美は所詮、軌道に乗ってから戻ってきただけのよそ者よ」
雨漏りする家のなかにいるときみたいに、心の内側にヒヤリとした何かが落ちた。耳に触れた瞬間に寒気がする、不愉快な四文字。よそ者。そうか、希美はまだよそ者か。
「あすか先輩は希美のことをよそ者だと思ってるんですか?」
「逆に、思ってへんやつがレアちゃう? 普通に馴染んでるけど、それでも部長や副部長みたいな役職を担えるほど人望あるかって言ったらそれは別問題よ」
「でも、中学のときは──」
「アンタがいま口にしたのが答えでしょ。ここは北宇治高校であって、南中じゃない。よその人間関係を持ち込んで、同じように活躍できると期待するのは無責任や」
時間を共有できなかったことを悔やむのは夏紀の専売特許だったのに、気づけば希美に奪われてしまった。あんな疎外感を、希美には味わわせたくなかったのに。
「部長のこと、支えてやってな」
ズルい人だ、と夏紀は口内で小さく舌打ちした。八割が照れ隠し、残り二割が素直に従うのは癪しやくだなというちょっとした反抗心だった。
初めからわかっていたのだ。それがあすかの頼みなら、夏紀は絶対に断れない。助けてもらったあの夏の日の恩を返せるタイミングを、夏紀はいつだってうかがっていた。
「そうじゃなくて、『アントワープブルー』っていうデビュー曲があんの。バンド名はその曲名からとってる」
時間は四分二十一秒。メンバー二人はいまより五歳ほど若く、野暮ったさが目立つ。
//后文照应
『僕は君になりたかった。
おめでとうって笑顔で言える、優しくて素敵で良い奴に。
僕は君になりたかった。
なりたかったのに。
結局、僕は君のなりそこないなんだ。
太陽とか月だとか 使い古された喩たとえで
勝手に理解した気になってんじゃねぇよ。
君に僕がわかってたまるか。
傲慢で臆病で身勝手な僕を。
期待なんてしたくないんだ、とっとと要らないと言ってくれ。
君の差し伸べる手が僕を永遠に苦しめるんだ。
君は僕を大事にしたい。
僕は僕を大事にしない。
めちゃくちゃに壊してやりたいんだ、今すぐに。
僕は君を。僕は僕を。』
//歌词的共鸣度在后面逐步提升
もしも優子に彼氏ができたら。ふと、四人でいたときに出た話題を思い出し、夏紀は自分の唇を片手で覆った。
きっと優子の恋人はいいやつだ。優子の人間を見る目は確かだから、育ちのいい爽やかな好青年を連れてくるだろう。夏紀にはちっとも理解できないファッションセンスで、夏紀にはちっともいいと思えない善良さで、優子の隣に当たり前の顔をして並ぶのだ。
休日にバーベキューをしたら準備なんかも一緒に手伝ってくれて、きっと面倒な仕事も愚痴ひとつ言わない。目が合った夏紀に向かって少し照れたように微笑む。「いつも優子がお世話になってます」なんて言われたところを想像して、架空の男に勝手にムカつく。何がお世話になってます、だよ。こっちはお前の何倍も優子のことを知っているのに。
架空の彼氏にマウントを取っている自分に気づき、その滑稽さに自嘲する。みぞれや希美に彼氏ができても、やっぱり夏紀はイラッとしてしまうのだろう。みぞれに彼氏ができたら寝込むと言った優子の気持ちがいまは少し理解できる。
「優子の彼氏は絶対髪型がマッシュ」
「なんで急に妄想始めたん」
「お洒落眼鏡とか、たまにしてそう」
「あー、そういうギャップは嫌いじゃない。顔は可愛い系がいいかも」
「やっぱりな。勝手に爽やか系イケメンと付き合っとけ」
「情緒不安定なん?」
「髭ひげが生えてそう」「フェスTをパジャマにしてそう」「高いスニーカーをコレクションしてそう」「事あるごとにお金より大事なものがあるって言ってそう」と、さんざんな言い草だ。
そんなみぞれが変わったのはいつのことだっただろう。希美が部に戻ってきてすぐのころは、みぞれは希美の顔を見ないように逃げ回っていた。希美から声をかけられることにおびえ、希美に笑いかけられることにおびえ、希美から優しくされることにおびえ……。それでいて、希美にはそのおびえがちっとも伝わっていなかった。
睫毛に押し込められたみぞれの瞳は、唇よりも雄弁に心情を語る。みぞれが恐れていたのは、希美にとって自分が取るに足らない存在だと思い知らされることだった。
優子はその言葉を優しく受け止め、みぞれの背中をなで、「無理せんでいい」と繰り返した。三人だけの秘密だ。南中出身のメンバーで生き残った、たった三人だけの秘密。
だとしたら報われないなと思う。優子がこれだけ心を砕いても、みぞれを変えられるのは希美だけなのだ。そのくせ、みぞれはそんな自分の状態を希美にだけは絶対に知られたくないと思っている。はたから見たら一目瞭然なのに、自分が秘密にしていればバレないと信じている。その無垢さが、夏紀の目にはひどく傲慢なものに映った。
だって、そこには希美の意思が欠落している。みぞれの想いはいつも一方的で、自己完結していた。希美は自分を傷つけると思ってるくせに、自分は希美を傷つけるほどの影響力がないと勝手に悟ったつもりでいる。
馬鹿じゃないのか。希美だって、ただの人間なのに。
あまりに快活な、翳かげりのない声だった。後ろめたさなんて微塵も感じさせない、ただの友達に対する答え。
気づいていないフリを希美が続けるなら、夏紀だってそれに付き合う。
優子がみぞれの味方になるなら、夏紀は希美の味方になるべきだ。
「あの子が自分なんてって卑下しちゃうのは、結局は自己肯定感が低いからなのよ。いまはそこそこマシになったけどね。後輩ができた影響も大きかったかな」
「後輩は可愛いからな」
「実体験?」
「ノーコメント」
「優子はほんま、みぞれのこと好きやな」
「好きやで。練習熱心でいい子やもん。しかもオーボエがえげつなく上手い。あんな才能あふれた子を前にしたら、誰だってダメになるのはもったいないって本能レベルで思うでしょ」
「思うかぁ?」
「夏紀も多分やられてるって。うちがいるからなんとなく抵抗してるだけで、二人きりになったらコロリよ」
「それだけ聞くと、あの子にある才能は、音楽云うん々ぬんっていうより他人を狂わせる才能やな」
「そのとおりでしょ。希美だって結局は狂わされてたやん」
おそらく、北宇治でもっともソロを経験したのはみぞれだろう。
「嫉妬してるんやろうな」
「八つ当たりしたくなっちゃう自分が嫌になるの。みぞれのこと、ちゃんと好きやのにね。それと同じくらい、多分──」
風が吹いて、希美の声はかき消された。だけど、夏紀はその言葉の続きがたやすく想像できていた。目を伏せ、希美はどこか困ったように笑っている。自分の感情を持て余しているのであろうことは夏紀にはすぐに伝わった。
「そりゃ、友情でしょ」
「あれが?」
「あれも」
だとするなら、友情の定義の範囲は海のように広い。水の入ったグラスを持ち上げ、夏紀はその中身を傾ける。
鎧塚みぞれは、
ふと、無理やりに渡された卒業アルバムのアンケートのことを思い出す。傘木希美にツキがないとするなら、鎧塚みぞれは視野が狭い。
夏紀が大好きな奏法は、アンプをゆがませて行うピックスクラッチだ。巻き弦になっている6弦と5弦の両方にピックを縦に押し当てて、そのままヘッド側にこすり上げる。「ギャイイィン」と耳元でけたたましい音が反響して、それだけで胸がすく思いがする。
鼓膜を揺さぶる音が、夏紀の意識を塗り潰す。理由のない焦燥も、嫌悪も、何もかもがかき消えて、ただ指先の動きにがむしゃらになる。
心の内側の、すっかり燃え尽きて灰になってしまった部分。そこに、小さく何かが芽吹くのを感じる。
今日の最低気温は三度、最高気温は十二度。降水確率はゼロパーセント、絶好の行楽日和だ。
ふふ、と笑ったみぞれの耳には真っ白なイヤーマフが目立っている。吹奏楽部の後輩たちが合格祝いにみぞれへ贈ったプレゼントだ。
「フリーフォール」
「そりゃ、空いてるからって理由で五回も続けて乗ったらそうなるって」
カラカラと笑う夏紀に、優子は信じられないという顔をしている。隣にいるみぞれはケロリとしていて、「もう乗らない?」と未練がましく後ろを振り返っていた。
優子が連続でフリーフォールに乗る羽目になったのは、このみぞれの無邪気なおねだり攻撃のせいだった。みぞれは一度気に入ったものに何度でも乗りたがる。
ちなみにフリーフォールの前には、ジェットコースターと急流すべりにそれぞれ三回ずつ乗っている。
//みぞれ!??太强了吧
最頂部は地上から八十メートル。「頂上からは園内の景色を一望できます!」と書かれた吹き出しの横には、夜と昼の風景差を比較する写真が並んで載っていた。
「夏紀と乗りたい」
「なんでもいい。着られたらそれで」
みぞれの普通は夏紀の普通とは少し違う。
「ギャップがあってええんちゃう。優子が卒倒するかもしれんけど」
B系ファッションに身を包んだみぞれを想像し、夏紀はクハッと弾けるような笑いを漏らした。
もしも夏紀が服を選ぶなら、みぞれをどうコーディネートするだろうか。黒のキャップにぶかぶかの赤のトレーナー、そこからのぞく短い丈のダメージジーンズ。足元はスニーカーがいい、明らかに大きめのやつ。ピアスをしてほしいけれど、みぞれはこれからも耳に穴を開けないだろう。耳にかけるタイプのイヤーカフがいいかもしれない。トカゲとかコウモリの形の、普段ならみぞれが絶対につけないものを選びたい。
それらを身にまとった想像上のみぞれが、キョトンとした顔で自身の袖を引っ張っている。いくら見た目をそれっぽく整えても、内面からにじみ出るみぞれの善良さは隠し切れない。
「わかる。どんな色でも夏紀だから」
「みぞれは人たらしやなぁ」
「夏紀は夏紀」
なんとなくみぞれは南中のメンバーに仲間外れにされていたような気がしていたけれど、それは夏紀の思い込みだったのかもしれない。
「フランスの天文学者のラカーユが、実験道具から名前をとった」
「へぇ、詳しいやん」
「希美が教えてくれたから」
──集中しているとき?
だって、怒ればいいのに。口汚く罵ればいいのに。
それはいまもそうだ。希美の味方は夏紀で、みぞれの味方は優子。そんな配役が自然と続いてしまっている。
「私にとって夏紀はいい人だから。それ以外に何が大事?」
光が灯ともらなくとも、夏紀はその光景を美しいと思う。目の前にいる相手も、もしかすると夏紀と同じ感性を持っているのかもしれない。
「みぞれはさ、希美のことどう思ってる?」
「友達」
即答だった。迷いのない答えに夏紀はたじろぐ。
「希美のこと好き?」
「好き」
「嫌になったりしたことない?」
「希美を?」
「そう、希美を」
「ない」
「一度も?」
「一度も」
「でも」
続いた台詞に、夏紀はハッと顔を上げる。一音一音を吟味するように、みぞれは句切るように言葉を紡いだ。
「希美を好きな自分は嫌いだった」
「希美は悪くないのに、勝手に苦しくなるから」
「それって、恋とは何が違うん?」
「そうだったらよかったのに」
地上から八十メートル。園内でもっとも空に近い場所で、みぞれは驚くほど静かに本音をさらした。
「付き合いたいとか結婚したいとか、そういう感情だったら諦めきれたから」
「諦めるって何を」
「希美を」
人差し指と中指。自分の指がぎこちなく震えたのが、やけに明瞭に感じられた。口内にどんどんとたまる唾を飲み込み、夏紀は正面からみぞれを見つめようと意識的に瞬きをこらえた。
みぞれの表情は穏やかだった。嵐が過ぎ去ったあとのような、傷痕が残る晴れやかさだった。
「ただ、一緒にいたかっただけ。でも、それがいちばん難しい。人間は、理由もなく一緒にはいない」
「理由っていうのは、恋人とか友達とか?」
「学校とか部活とか」
つけ足された内容は、夏紀が挙げたものに比べて他人行儀だった。そんなものを理由と呼ぶのか。夏紀たちがみぞれと一緒にいる理由も、彼女のなかではそうしたものに分類されてしまうのか。それは腹立たしい。夏紀はみぞれだからこうしていまも一緒にいるのに。
「だからさ、うちがいいやつのフリできるのはみぞれのおかげってこと」
「私も好き。高いところが好き。空を飛びたい」
もしも自分の背中から翼が生えたって、夏紀はきっと空を飛べない。屋上の柵にもたれかかって、脚を伸ばして、それで終わりだ。だが、みぞれは違うのだろう。彼女はためらいなく空へと飛び込む。自分が落ちるところを想像すらしないし、皆の心配をよそに、器用に飛んでみせるのだろう。
みぞれが空を飛べるとするなら、希美はどうなのだろうか。ともに空を飛ぶのか、夏紀と同じように屋上から飛び立つみぞれを眺めるだけなのか。
みぞれの背中から真っ白な翼が生えているところを想像する。白鳥みたいな立派な翼だ。傷ひとつなく、力強く羽ばたくことのできる翼。それに違和感がないことに、なぜだか少しゾッとした。自分はみぞれをなんだと思っているのだろう。
「また来たい、みんなで」
みぞれの爪先が、コツンと分厚い壁を叩く。彼女の白いブーツの底は確かにゴンドラの床に着いていた。強張っていた肩の筋肉が、音もなく解けていくのを感じる。夏紀は無意識に頬を緩めた。
「何度だって来たらええやん。友達なんやから」
「友達」
おうむ返しにされた言葉に、夏紀は「そーそー」とうなずいた。人差し指と中指。右手と左手でピースを作り、それを胸の前でくっつける。
「四人は友達」
みぞれはこちらを凝視していたが、やがておずおずと同じポーズを真似してみせた。狭いゴンドラ内に流れる沈黙。冷やかされることを前提としたコミュニケーションは、こういうときに恥ずかしさで身体の内側から爆発しそうになる。
くすぐったそうに身をよじらせ、みぞれは口元を綻ばせる。
「やっぱり、観覧車が好き」
そのままみぞれは空いている希美の隣へ腰かける。夏紀とみぞれで優子と希美を挟んで座るかたちだ。
「でもあれやんな、みぞれって確か中学のとき、吹奏楽部の合宿で優勝してたよな。肝試し大会」
「ベストタイムやってん。そう、確かあれ、お化けにまったく気づいてへんかってさ。優子なんか大騒ぎやったのに」
懐古的な空気になると、途端に夏紀だけが締め出される。無自覚に発生する疎外感にはとっくに慣れてしまった。
「私、ポップコーンが食べたい。しょっぱいの」
「おお、みぞれが希望を言うやなんて……。いますぐ行こう。バター醤しよう油ゆ味のやつが近くで売ってたから」
//第2话开篇插图

優子の手が夏紀の背を軽く叩く。休日だという理由で、今日の彼女の爪先は薄い水色のマニキュアで彩られている。部活時代だとありえないチョイスだ。部長としての優子はきちんと規律を守るほうだったから。
「いや、うちっていうよりみぞれが一方的にな? で、希美やったらどうするかなと思って」
「何が?」
「もしも自分の背中に羽根が生えたらさ、空を飛ぼうって思う?」
「羽根の形状による。サイズとか材質とか」
「えー、そういうこと気にしちゃう?」
「いちばん大事ちゃう? 信頼できないものに命はかけられんやんか。蝶ちようとかトンボの羽根やったら信頼できひんな、コウモリもちょっと怖いかも。鳥もなぁ、あんなもんでほんまに空飛べるか? ってなると思う」
//夏纪是个很现实的人 但这本看完觉得希美更加现实到无情 从选择北宇治完全不考虑社团因素和南中友人的因素 到这个答非所问钻牛角尖到羽翅规格材质的角度 实在是....
「じゃ、どんな羽根なら信頼できる?」
「結局どんなのでも嫌かも。自分の足がいちばん信頼できる」
「つまり、空は飛ばないってことね」
「みぞれは飛びそう」
「あー、やっぱ希美もそう思う?」
「飛べへんかもしれんって思いつきもしなさそう。優子も飛ぶタイプやと思う。あの子はガチガチに地上で練習してから、満を持して空を飛ぶタイプ。で、夏紀に『いまどき地面歩くとかダッサ』とか言うてくる」
「そんな喧嘩売られたらムカつくからうちも飛ぶわ」
「夏紀はさ、優子となら空を飛べるタイプやな」
「そういやここの遊園地、バンジージャンプもあったで」
「やらんからな」
「冗談やん」
//刚想说玩垂直升降不如蹦极....
「部活ロスや、お互い」
「変わったやん。四人のなかでいちばん変わったのが夏紀やと思うわ」
「なぁ、バンド名はどうするん?」
「まだ決めてない」
希美の隣で、夏紀はわざと大股に前進する。バンド名は決まってない。これからの予定も、その先の未来だって、まだなんにも決まってない。
第二話 鎧塚みぞれは視野がせまい。
(それこそが彼女の彼女たる理由)
自室に飾られた木製フレームには、先日の遊園地で撮影した写真が納まっている。イルミネーションで彩られた園内の風景をバックに、四人はレンズに笑顔を向けていた。近くを歩いていたスタッフにお願いして撮影したものだ。
冬は嫌いじゃない。冷たさと痛さは似ていて、浸っていると心地いい。
二月も半ばを過ぎ、登校する機会も残りわずかとなった。あと二週間後には卒業式を迎え、夏紀たちは北宇治高校の生徒ではなくなる。それが寂しいのか、どうでもいいのか、清々するのか。自分の気持ちであるはずなのに、声に出せばどれもが本心からほど遠いものに感じた。
アントワープとはベルギーの北西部にある州都のこと。アントウェルペン、アンベールとも呼ばれる。この都市で使用されていたことがアントワープブルーの名前の由来らしい。
//安特卫普(荷兰语:Antwerpen;德语:Antorf;法语:Anvers)是比利时最重要的商业中心、港口城市和佛兰德的首府,或译为央凡尔(法语)。via中文维基
「店がルミナリエみたいになるーって」
ルミナリエとは「神戸ルミナリエ」、毎年十二月になると神戸市の旧居留地で行われる祭典のことを指す。阪神・淡路大震災の犠牲者への鎮魂と都市の復興への願いを込めて平成七年から開催されている。ルミナリエという言葉はイタリア語でイルミネーションという意味で、その名のとおり、期間中は街がきらびやかな電飾で飾りつけられる。
「みぞれの家って金持ちやしなぁ」
実際に家に行ったことはないが、なんとなく想像はできる。なんせ、家にグランドピアノがある環境だ。夏紀の家のような平凡を絵に描いたような家庭とは大違いだろう。クリスマスのイルミネーションだってとんでもないのかもしれない。
「どこに買いに行く?」
「四条でええんちゃう?」
中世古香織といえば、優子が傾倒していたトランペットパートのひとつ上の先輩だ。卒業したいまは看護学校に進学した。
「そりゃ香織先輩はずっと見目麗しいけど、そういうことじゃなくて、中身が違ったというかさ。もう高校生じゃなかった。大人やった。それがなんか、寂しいなって」
「一つひとつの当たり前に、さよならしてるような気分」
「さよならアントワープブルー」
結果を求められない演奏というのは、なんだか不思議な感じがする。吹奏楽部では自分のミスが全部員の連帯責任となって跳ね返ってきたけれど、ツーピースバンドだと自分のミスはたった二人だけのものだ。
優子とカラオケ店で練習した日からまだ三日もたっていない。おおかた、優子が勝手に夏紀のスケジュールを希美に伝えたのだろう。どうせこの時期は暇だから、予定が埋まるのはありがたいっちゃありがたい。
三月になればほぼすべての入試が終わるため、一気に予定が埋まってしまう。吹奏楽部の三年生で卒業旅行にも行くし、クラスの友達とも出かけなければいけないし、時間も金もすぐに足りなくなる。だから、時間を持て余すなんて贅ぜい沢たくなことができるのはいまだけだ。
希美と優子は夏紀と似たような格好だったが、みぞれだけは違った。彼女が着ているセーターは、いまだかつて見たことがないくらいダサかった。顔だけの猫が目からビームを出し、ビルを破壊しているイラストが深緑色のセーターの中央にデカデカと描かれている。やけに太いフォントで『ゴゴゴゴゴゴ』と書かれているのもダサさポイントを加点していた。
「みぞれ、そのセーターどうしたん」
「汚れてもいい服があるかお母さんに聞いたら、これを出してくれた」
//这啥衣服wwwwwww快映像化

「髪型が違っても、夏紀」
「夏紀ってさ、みぞれの扱い上手いよな」
「普通や普通」
「みぞれ、飴ちゃんあげるからこっちおいで」
「優子はみぞれをなんやと思ってるんや」
いつの間にか夏紀の隣に立っていた希美が、ポンとこちらの背を叩いた。ダウンジャケットの上から彼女が背負うリュックサックはやけに大きく、これから登山にでも行くのかと錯覚しそうになる。
希美がリュックサックから取り出したのは、二メートル四方のブルーシートだった。すでにペンキがこびりついているところを見るに、これまで何度か使ったことのある代物なのだろう。四人で協力して広げ、飛んでいかないように四隅には重石を置く。その上に希美が広げたのは、長方形の形をした真っ白な布だった。縦一メートル、横一・五メートルのそこそこ大きな布だ。
「これ、水性塗料やから」と希美が笑いながら言った。同じペンキでも水性と油性で違いがあるらしい。
缶の中身をのぞき込みながら、優子が感心したようにつぶやく。液体の青は、スマホの画面で見たときよりもずっと暗い色をしていた。銀色の缶のなかに、真夜中の海が沈んでいる。濃縮された青ってこんな色なのか、と夏紀は呑気に考える。青というよりも黒と呼んだほうがいい気がする。
//灰暗色调和各个心情 大会结果 情绪相互照应
その青は、狂おしいくらいに自由だった。
狭苦しいペンキ缶のなかに押し込められていたときとは比べものにならないほど、透き通っていて明るい。徹夜したときに窓から見える日の出前の朝の空気みたいな、澄んだ光をはらんでいる。
//然后预示光明的未来
希美が満足そうにうなずく。それを眺めていたみぞれが、大胆な手つきで布を塗った。慎重に細かく色を埋めていく優子とは対照的に、みぞれは右から左へと刷毛にのったペンキが続く限り塗り進めていく。そのくせ、塗り跡はみぞれのほうが綺麗に仕上がっているのだからすごい。ある種の才能かもしれない。
//みぞれ怎么干啥都厉害doge
一枚の布をすべて青く塗りたくるのには、結局一時間ほどかかった。
「夜になる前の空みたい」と足裏をタオルで拭いながら希美が告げ、
「海の底に似てる」とみぞれは静かにつぶやく。
「夏紀がよく着てるデニムってこんな色ちゃう?」と優子がこちらを見ながら言い、
「情緒がないな」と夏紀は笑った。
自分にはこの青色が何に見えるだろうか。目を凝らしてみると、濃い青と薄い青が重なり合っているのがわかる。氷の下に眠る海? 宇宙が始まる一秒前? 探るうちに思考が詩的になってしまって、夏紀は口をつぐんだ。
ただそこにあるだけで綺麗な色だと思った。
//后文照应
あいこが続くこと三回、四回目のジャンケンでようやく優子とみぞれが近くのスーパーに買い出しに行くことが決定した。
罪滅ぼし。その言葉を、夏紀が希美に告げることは永遠にないだろう。あの日、希美の背中を押した後悔は、自分が抱えるべきものだった。誰にも奪われたくない。たとえその相手が希美であっても。
「そんなんあったっけ。あなたにとってあなた自身の印象は? とかそういう質問しか覚えてない」
「夏紀はなんて書いたん?」
「そもそも回答してない。希美は?」
「うちは、ポジティブ器用貧乏って書いたな」
「いい声やな」
シンプルな称賛に、夏紀は照れをごまかすように頬をかく。「そうやろ」と当然の顔で肯定するには、夏紀の面の皮の厚さが少しばかり足りなかった。
名案だろうと言わんばかりに、優子が気の強そうな両目をこちらに向ける。最後に行った身体測定では夏紀と優子の身長はぴったり同じだったから、こうして向かい合うと目線だって同じになる。
吉川優子という女は、台風の目みたいなやつだった。初めて出会ったころからずっとそうだ。コイツはどこにいたって多くの人間を惹きつけ、巻き込んで、いろいろなものを引っかき回す。
そして夏紀たちが三年生になったとき、北宇治は強豪校としてのシステムを完成させつつあった。
「希美たちが部活を辞めたときにね、トランペットだけっていうのは怖いなって思った」
「怖いって?」
「たとえばさ、トランペットでは絶対に負けたくないって思っちゃったら、それを吹く場所をなくしたときのダメージすごいやん? 希美はフルートやからマイ楽器を持ってたけどさ、じゃあうちがもしチューバパートの人間やったら、部活を辞めることはそのままイコールでチューバを辞めることになっちゃうやん。部活で使う楽器は学校の持ち物やから」
「うちはトランペットやったからマイ楽器って選択肢もあるにはあってんけど、でも、頼るものを分散化しようと思ったの。いろんなものを好きになって、いろんなものを居場所にして……。そうしたら、何かを続けられなくなったときに別の何かが自分を助けてくれるやろ? だからさ、ギターをやりたいなって」
大学生になったら、夏紀と優子はどうなるのだろう。部活という理由がなくなり、授業という枠もほとんどなくなったいま、毎日顔を合わせる必要なんてなくなった。それでもいまもなお二人を密接につないでくれているものは、演奏発表という終わりの存在するイベントだった。
吉川優子の円滑な部活運営は、部長が彼女でなければ成立しない。
//部活運営術ry 传承下去的黄前流人心掌握术
あすかが夏紀を副部長として指名したのも、こうした流れになることを見越してのことだろう。あすかが卒業しても、夏紀はずっと彼女の手のひらの上で踊らされ続けている。
ジャージにTシャツ。今日の夏紀はラフな格好をしている。前にいる優子も似たような服装だ。黒地のTシャツの胸元には、『I must be cruel, only to be kind』と紫色の英文が印刷されていた。
そういえば、と夏紀が自分のTシャツを見下ろすと、セピアカラーの遊園地の写真の上に『Love, the itch, and a cough cannot be hid』とピンク字の英文が躍っていた。意味は知らない。そもそも夏紀は服を買うときに英文の内容を気にしたりはしなかった。たまにとんでもない意味だったりすることがあるので、本当は注意したほうがいいのだろうけど。
「あ、頭をなでてやろうか」
思いついたことをそのまま口に出せば、優子は「いらん」と即答した。その割に彼女の前頭が重そうに傾いていたものだから、夏紀は手を伸ばすことにした。優子の後頭部に手を添え、そのまま抱き込むように小さな頭を肩口に引き寄せる。あれだけ憎まれ口を叩いていたくせに、優子は抵抗しなかった。
夏紀の肩に、彼女の両目が押しつけられる。熱の塊を、Tシャツ越しに意識する。
「……疲れた」
本当は夏紀にだってわかっている。夏紀がいなくたって、優子は自分の感情に折り合いをつけられる。そういう術を知っているやつだ。だからこれは、夏紀の自己満足なのだ。優子の部長としての仮面をバリバリと剥がし取って、破壊し尽くして、それでもって彼女が内に秘めたもろい部分を無理やりに引きずり出してやる。
//很久丽ry
なんでそんなことをするのかと聞かれたら、ムカつくからと夏紀は答える。二年生のときには剥き出しだったはずのそれが、部長に就任した途端に完璧に隠されるだなんて腹立たしい。
泣いてしまえ。
そう口に出してしまえば、優子の涙は自分の前から失われてしまうだろう。なんせ彼女はひどい天あまの邪じや鬼くだから、優しく甘やかしたところで素直になったりしないのだ。
そして、その事実に救われることも。
「もう大丈夫」
優子の手が、夏紀の鎖骨辺りを軽く押す。立ち上がる彼女は憑つき物が落ちたような、どこか晴れやかな表情を浮かべていた。「そっか」と夏紀はうなずく。それ以上の言葉は互いに必要としていなかった。
//为没有人看见这一幕而不用感到害羞 也为没有人看到优子软弱一面而得以维持下去
何か英文が書かれていたことは覚えているのに、それがどんな内容かまではすっかり忘れてしまっている。夏紀の脳内に収納された記憶というのはたいていそうで、どこか細かいところが欠けている。
アコースティックギターとエレキギターじゃ、そのまま弾いたときの音が全然違う。アコースティックギターはボディー内が空洞だからよく音が響くし、エレキギターは中身が詰まったままなので弦だけの響きになる。
だけど夏紀は、こうして密やかに鳴り響くエレキギターの旋律も好きだった。
「卒業証書、授与」
卒業式の日、天気は快晴だった。
代替品があふれている世の中だ。替えの利かない人間なんてきっといない。
この世界は、夏紀が想像するよりずっと上手くできている。
こちらに証書を差し出す校長にとって、自分なんて取るに足らない存在だろうなとぼんやりと考える。彼は夏紀とほかの生徒を区別していないだろうし、それが悪いことだとは微塵も思わない。だって、世の中ってそういうものだし。
ホームルームを終えてクラスメイトたちに別れを告げたあと、元吹奏楽部員たちは中庭に集められていた。一、二年生にとって今日は休日なのだが、式の手伝いがある吹奏楽部員は強制的に登校させられている。そのため、見送り率がほかの部活よりも高いのだ。
この鳥かごは夏紀だけじゃなく、三年生部員全員に用意されているようだった。
オーボエパートのみぞれは泣いてはおらず、代わりに後輩が人目も憚らずに大泣きしていた。ハンカチを差し出すみぞれの表情は普段よりもどこか柔らかく、先輩らしい振る舞いもできるのだなと夏紀は密かに感心した。
ユーフォニアムパートの後輩たちも、夏紀の卒業を惜しんでくれた。少しひねくれた性格の一年生の目は赤かった。それをからかってやれば、彼女は矛先逸らしとばかりに「久美子先輩なんて、演奏の途中で泣いてましたよ」と隣にいる先輩の恥ずかしいところを暴露した。久美子はごまかすどころか、「お別れだと思うと寂しくて」と目を潤ませ始めた。この二人のやり取りは、どちらが振り回してどちらが振り回されているのかたまにわからなくなるのがおもしろい。
後輩たちとの会話は楽しかった。途中からチューバパートとコントラバスの面々も加わり、改めて低音パートでお別れ会をしようという話も決まった。これが今生の別れでないと確信した後輩たちは、明らかにほっとした様子でほかの三年生に話しかけに行った。夏紀はそれを見送る気でいたのだが、なぜか久美子だけがその場から一向に離れようとしなかった。
おびえる久美子を見ているとムカついたから、自分が不愉快な気分にならないためにフォローした。
「救われたんですよ、私は夏紀先輩に」
それに、できることなら最後までカッコいい先輩のフリをしたいじゃないか。
「そう言ってくれるなら、部活に入った意味があったわ」
その日の夕食は家族で焼き肉を食べに行った。一人三千円の九十分食べ放題コース。かしこまったお祝いなんて中川家らしくないし、夏紀だって望んでいない。
はち切れそうなくらいに腹を膨らませ、夏紀たちは帰宅した。机の上には今日の戦利品がうずたかく積まれている。筒に入れたままの卒業証書、書き込みで余白がなくなった卒業アルバム、後輩からもらった鳥かごアレンジのプリザーブドフラワー、イラストとメッセージであふれた色紙、一人ずつ渡された手紙たち。
そのいちばん上にある封筒をつまみ上げ、夏紀はベッドへと寝転がった。送り主の名前は吉川優子。今朝、一緒に登校した際に押しつけられたものだ。どうせ明日もカラオケ店で会うというのに、手紙だなんて律義なやつだ。
封筒の口はラッパのシールで閉じられている。夏紀はそれを手に取り、蛍光灯の光にかざした。本当は、登校しているときに見てやろうと思っていた。だが、優子が自分のいないときに読めとしつこく念押ししてきたから読むのは後回しにした。
シールを爪先で引っかくと簡単に剥がれた。なかに入っていた便せんは意外と枚数があった。夏紀は身を起こし、ふたつ折りにされた紙を開く。『中川夏紀さま』なんて書き出しから文章は始まっていた。
//第3话开篇插图
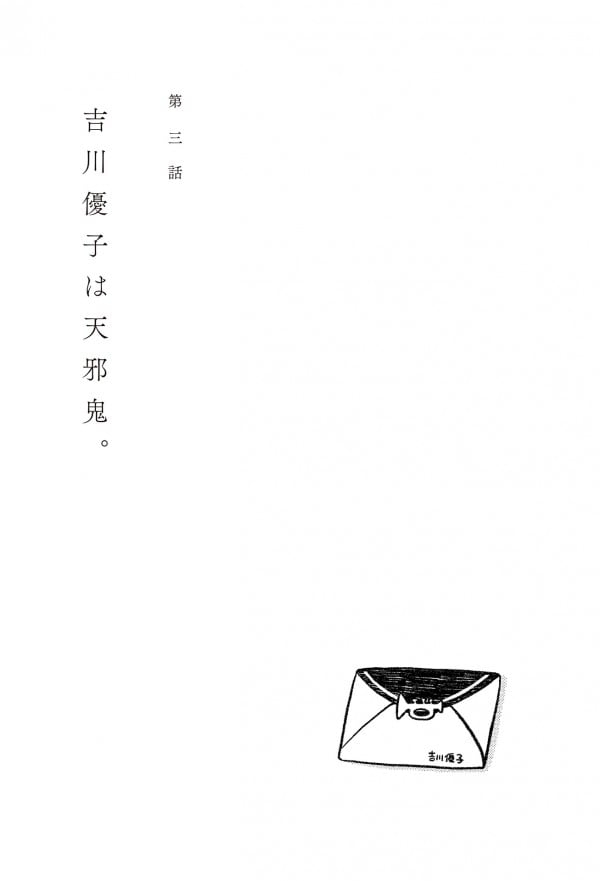
明日は卒業式ですね、なんてかしこまって書くのもなんかあほらしいな。いや、ほんまはこんなもんを書くつもりなんてまったくなかったんやけど、香織先輩が去年、卒業式の日にあすか先輩に手紙を書いたっていうから、私もそれにならってみた。つまりこの行為は香織先輩へのリスペクトから発生したもんやから、そこらへん勘違いせんように!
それにしても、もう卒業やで。めっちゃやばない? ついこのあいだ一年生やった気がするのに、我々も春から大学生ですよ。はっや! この一年、自分ではがむしゃらにいろいろと頑張ったつもりやねんけど、こうして振り返ってみると、もっとああすればよかったとかこうすれば上手くいったかもとか、自分のあかんところも見えてくるね。ま、いまさら言うてもしゃあないことやけど。
関西大会のあと、一緒に帰ったこと覚えとる? アンタさ、わざわざ遠回りしてうちについてきてさ。余計なお世話やとか言っちゃったけど、ほんまはうれしかったよ。ありがたかった。どっか行けって言って、それでもそばにいてくれるやつがおるってのは感謝すべきことやなとずっと思ってました。言葉で伝えられんかったけどね。アンタすぐ茶化すし、お礼とか言わせてくれんから。
うちはこの一年、ずっと部長でした。起きてから寝るまで、ずっと北宇治高校吹奏楽部の部長。もうね、切り替えのスイッチがぶっ壊れてたよ。去年の部長とか副部長はどうやって上手く切り替えてたんやろね。うちにはさっぱりわかりません。
というか、いま振り返ると、そういう自分に酔ってたところもあったかも。頑張ってるうち、偉い! みたいな。でも、それを続けられたんは、アンタがうちの部長スイッチを毎回オフにしてくれてたからやなって、引退してから気づいた。アンタがおらんかったら多分、やっていけんかったよ。だからー、そのー、あれですよ。素直に認めるのもシャクで、いままであんま言わんかったけど……あー! 勢いがないと書けへん! つまりまあ、ありがとよ! アンタが思ってる以上にこっちは感謝してるぞ! ってことです! 以上!
なんか、いっぱい書いてて不安になってきたけど、ほんまにこれ、アンタに渡せとるんやろうか。恥ずかしさで死にそうよ、いやほんまに。書いてるうちがこんなにつらい目に遭っとるんやから、読んでるアンタも恥ずかしくなって苦しめばええと思います。いままでありがとう! アンタのこと結構好きやぞ! ……どう? 照れた? ざまあみろ!
とまあ、長々としょうもないことを書いててもしゃあないので、この手紙はここで終わりにします。これから先、こんなこっぱずかしい手紙を書くことは二度とないでしょう。うちの黒歴史になること間違いなしなので、読み終わったらすぐさま燃やすことを推奨します。絶対に取っておいたりしないように!
便せんを再び折り畳み、夏紀は封筒のなかへと戻した。片づける気にはどうしてもならなくて、そのままベッドの隅に置く。
「恥ずかしいやつ」
前に優子と動物映画を見たときは涙を流してしまったし。
今日はもう眠ってしまいたい。イベントの本番まで一週間を切っている。
今日のスケジュールは至ってシンプルだ。十三時から優子とカラオケ店で練習。以上。
せっかく卒業したし、おめかしでもするか。見せる相手は優子だけだがそれでもいい。
使い終わった食器を片づけ、夏紀はいそいそと身支度を始める。パステルピンクのタイトなデニムスカートに、だぼだぼした黒のトレーナー。靴下もスニーカーも鞄も黒に統一しよう。母親から卒業祝いに贈られたメイクボックスを開けて、化粧なんかもやっちゃったりして。
下地を塗って、ファンデーションをして、眉を整えて、アイシャドウやらアイライナーを使って。鏡に映る自分を凝視しながら、オレンジ色のリップを塗る。できあがった自分の顔を見て、なかなかいい仕上がりなんじゃない? とちょっと角度を変えてみる。ふふんと鼻を鳴らして、満足して──そして、すべてがどうでもよくなった。
これが燃え尽き症候群ってやつですか?
べつに、寂しいわけじゃない。悲しいわけでもない。ただ、虚むなしい。あれだけ濃密な時間をともにしたというのに、いったい自分に何が残ったというのだろう。すぐ間近にいた人間も、いつの日か思い出のなかの住民になってしまう。音楽室に集まって同じメンバーで合奏することは、これから先、二度とない。
熱い何かが頬を伝って、夏紀は反射的に指で拭った。それが涙であることに気づくのに、数秒のタイムラグがあった。瞬きすると、瞼の縁から押し出されてぼろぼろと涙があふれ出す。いまさらかよ、そうつぶやこうとして唇が震えた。
呼吸のリズムが崩れ、夏紀はソファーの上にあったクッションを抱きしめる。涙腺の蛇口が壊れてしまったのか、涙があふれて止まらない。「バスタオルが必要か?」とイマジナリー優子が揶揄する。必要かもしれないなと夏紀はクッションに額を押しつけながら思った。
ひどくなる嗚咽をこらえようともせず、夏紀はただ泣き続けた。涙の条件は一人になることだったのかと、夏紀はようやく思い知った。
なんせ、彼女は意地でも夏紀の隣に並ぶから。
肩幅に足を開き、夏紀は優子の顔を見やる。コクンとうなずかれ、互いの準備が済んでいることを確認する。メトロノームは使わない。曲のテンポを決めるのは、最初に奏でる四分音符の連続だ。
夏紀の右手が一、二、三、四、とリズムを刻む。その直後、優子のギターが加わってくる。それぞれの担当は、優子がメインメロディーを担うリードギター、歌う夏紀がバッキングだ。
見てみたかった、あの子と同じ世界を。
いななきに似たギターの旋律。優子が夏紀を見る。まっすぐな眼差しが夏紀の両目を頭蓋骨ごと貫いた。よそ見なんて許さないって、幼稚な愛を叫んでいるみたい。
「いや、青がいい。うちがやったげるからさ、アンタの家泊まっていい?」
//突击ry
「ウチのオカン、優子のこと気に入ってるもん。礼儀正しい子やわぁって」
「この前家に遊びに行ったときにちゃんと手土産持っていった甲か斐いがあったな」
//草
優子が夏紀の家に泊まりに来たのは、その三日後だった。
夏紀の自室に入るなり、優子はニヤニヤしながら木製フレームの写真立てを手に取った。遊園地に行って、四人で撮ったときの写真だ。
「なんかさ、演奏会が終わったらほんまに卒業やなって気がせん?」
グラスを傾けながら、優子がしんみりとつぶやく。
「卒業式はもう終わったやん」
「そうやねんけど、演奏会があるうちはまだ高校生活の延長って感じもあったっていうか、さ。ほんまに……ほんまに、終わるんやなって思う」
「何が」
「うちの高校生活が」
「正直なこと言うてさ、うち、みぞれのこともちょっと苦手やった。だってあの子、自分の振る舞いが希美の目にどう映ってるか、全然気づいてないんやもん。苛つくやんか、そんなん。なのにあの子、うちに平気で言うねん。『夏紀はいい人』って」
ずっと、許せないのだ。あの日、希美の背中を押した自分自身を。皆が空気を読んで駆け出したとき、遠くから冷笑した自分自身を。だから夏紀の優しく見える振る舞いは、すべてが罪滅ぼしなのだ。誰かの一生懸命を馬鹿にしていた、あのころの自分を許せないだけ。
「アンタがどう思ってるかなんて、それこそどうでもいいっての。優しくされたほうはうれしくて助かって、頑張る理由になった。だからアンタに感謝してるの。こっちの感謝をねじ曲げようやなんて、それこそ身勝手な理屈やな」
「いくらでも代わりがいるなかで、うちはアンタを選んでこうやって一緒にいるワケ。代わりがないからじゃなくて、代わりがいくらあってもアンタを選ぶ。一緒に音楽やるのも、こうやって過ごすのも、夏紀と一緒がいいよ。それが悪いこととはうちにはどうしても思えへん」
視界は青かった。夜になる前の空みたいな、海の底にいるみたいな、光をまとった青色が小さな世界を満たしていた。
//照应 哭了
「そんな恥ずかしいこと、堂々とよく言えるな」
「そういう流れだったでしょうが! いま!」
「ま、うちだって選ぶならアンタ以外考えられへんな」
「ソッチのほうが千倍恥ずかしい!」
***
本番当日はあっという間にやってきた。
会場となるカフェは地下にあり、窓は一切なかった。太陽光は差し込まないが、代わりに間接照明を大量に配置することで物々しい雰囲気になることを避けている。
打ちっ放しのコンクリートの壁には電飾ケーブルが飾りつけられており、会場内をほんのりと青く染め上げていた。十五時から十八時まで、今日は夏紀たちによる貸し切りだ。開演は十六時のため、いまは演者と手伝いのスタッフしかいない。
先ほどまで菫との会話に花を咲かせていた希美が、大股でこちらに歩み寄ってくる。それを後ろから追いかけるみぞれの髪型は、珍しくポニーテールだった。
//!!!
コクリと首を縦に振り、みぞれは急にピースサインを作り出した。右手と左手でピースをし、人差し指同士を胸の前でくっつける。
「W?」
「なんのポーズ?」
不思議そうな顔をする希美と優子を無視し、夏紀もまた同じポーズをしてみせた。それを見たみぞれの唇が満足そうに綻ぶ。込められた意味を知っているのは、この場では二人だけだった。
「そういう暗号? 秘密結社みたいやな」とトンチンカンなことを言いながら、希美がみぞれのポーズを真似する。やっていないのは残り一人だ。促す三人の視線を受け、「何このノリ」と唇をとがらせながら、優子がゆっくりと両手でピースサインを作る。
四人は同じポーズで向き合い、誰からともなく笑い出した。本番の開始時刻が、緩やかに迫っていた。
//「四人は友達」
//最后的插图照应

夏紀は優子を見る。そして、優子も夏紀を見る。それだけで準備はもう済んでいた。
マイクに近づく自身の唇が、今日の二人の名前を紡ぐ。
「さよなら、アントワープブルー」
カウント代わりに動くピックが弦を静かにかき鳴らす。
長くて短い、四分二十一秒の歌。
その始まりを告げる爪先は、どこまでも自由な色をしていた。
第三話 吉川優子は天邪鬼。
(そしてそれはお互い様)
エピローグ
金賞と書かれた賞状を掲げ持つ優子は清すが々すがしい笑顔を浮かべていて、その目が赤く腫れていることなんて写真を見ただけじゃ誰も気づかないだろう。胸を張る彼女の姿を、夏紀はいまでも誇らしく思う。その傍らに寄り添うようにして立つ、自分自身の振る舞いも。
ここに写っているのは、部長と副部長しての優子と夏紀だった。
「松本先生が人気だったんだよね」
「うちは絶対滝先生が一位やと思ったけどなぁ」
//所以顺位是怎样

13 あなたの自分自身への印象は?
無意識に伸ばした指が、印刷された文字をたどった。この問いに対する答えを、自分はずっと探し続けていたような気がする。
もしもいま、手元に回答用紙があったならば、夏紀は迷いなくこう書いただろう。
中川夏紀は、身勝手だ。
でも、そんな自分も嫌いじゃない。
减少了肢体描写
可以ctrl+f一下"背" 看武田描写了多少次敲打//推人背 我基本都摘下来了ry

这句话准确的意思是
想要交往或是结婚什么的 如果我抱着的是那样的感情 那么早就放弃了